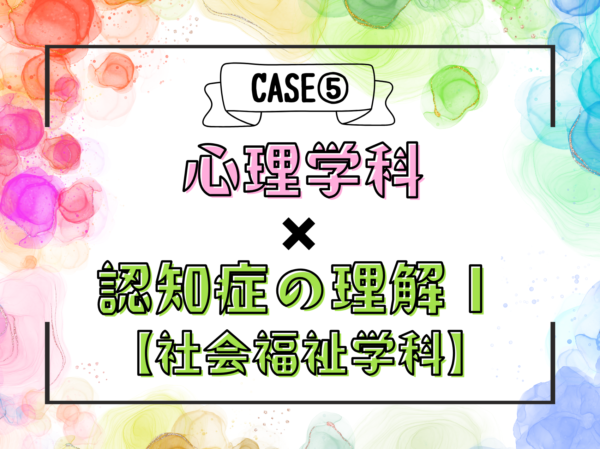
保護者の方にもおすすめ
474
2025.7.25
心理学科2回生Oさん×認知症の理解Ⅰ 神戸女子大学の特徴のひとつに、2024年度から始まった『自分色パレット』(正式名称:テーマ型ユニット)があります。 ※2025年6月取材時 『自分色パレット』とは… 学生が興味をもった「知りたいこと」について、所属する学科以外で開講される講義を受講することができる制度です。自分が所属する学科の講義≒専門分野での学びに加え、所属学科以外の講義から培った知識を合わせることで違った視点でモノを捉え、考える力を養うことができます。 社会福祉学科の科目を履修している心理学科2回生Oさんに、学びのきっかけや気づき、将来の展望についてお話を伺いました。 ──まずは自己紹介と、心理学科を選んだ理由を教えてください。 心理学部心理学科2回生のOです。高校までは数学など、明確な“正解”がある学問を学んできましたが、大学では「人によって答えが異なる」学問に惹かれて、心理学科を選びました。 ──「自分色パレット」というテーマ型ユニット科目についてはご存知でしたか? 名前は聞いたことがありましたが、内容までは詳しく知りませんでした。 ──社会福祉学科の「認知症の理解Ⅰ」を履修された理由は? 将来は公認心理師の資格を取り、病院で働きたいと考えています。そのためには、心理支援だけでなく、福祉の視点も必要だと感じて、履修しました。 ──受講前と後で授業の印象にギャップはありましたか? 内容面はシラバス通りでしたが、授業の雰囲気には驚きました。普通の講義形式かと思いきや、冒頭に自分で調べた認知症トピックを発表したり、みんなでストレッチしたりと、参加型の授業で、良い意味で予想と違いました。 ──印象に残っている内容はありますか? 認知症には一つの型だけでなく、様々な種類や症状があり、患者さん一人ひとりに合った理解と支援が必要ということが印象に残っています。 ──グループワークや他学科の学生との交流はありますか? 発表は多くないですが、意見交換は活発です。他の授業よりも、他学科の学生との関わりがあるように感じます。 ──履修を通じて、自分自身の考えや視野に変化はありましたか? 大きく変わりました。認知症は患者さん本人だけでなく、家族や周囲の人も心理的に苦しんでいるという現実に気づき、心理支援の在り方を改めて考えさせられました。 ──この授業を友達や後輩におすすめするとしたら、どんなポイントを伝えますか? 心理支援は、医師や看護師など周囲の支援者と協力して成り立つことを実感しました。視野を広げたい人にはとても良い機会だと思います。 ──授業を通して、もっと学びたいと感じたことは? 「認知症」と「パーキンソン病」の関連について興味を持ちました。祖母がパーキンソン病を患っていたこともあり、あのときもっと知識があればと思った経験から、学びを深めたいと思っています。 ──後期には社会福祉学科の科目の「発達と老化の理解」も履修されていますね。 はい、関連する分野をもっと学びたいと思い、履修しました。将来、病院勤務を希望していることもあり、現代の高齢社会において重要なテーマだと感じています。 ──現在の「自分色パレット」のテーマで気になるものはありますか? 現在も履修している社会福祉学科のユニット「老化と認知を理解して超高齢社会にそなえる」や、健康スポーツ栄養学科のユニット「運動、栄養、健康の観点から人の行動を科学する」が気になります。 ──今後、開講してほしいテーマはありますか? 「犯罪心理学」など、もっと心理学寄りの内容も増えたら嬉しいです。 ──最後に、「自分色パレット」に対する印象を改めて教えてください。 あまり詳しくなかったのですが、こうしてインタビューをしているうちに、学部の壁が思っていたより低く、自由に学べる環境なんだと感じました。もっと多くの学生に知ってもらいたいです。 学びに“正解”はひとつじゃない。 多様な学びの中で、自分らしい答えを探す大学生活。その中で「自分色パレット」は、多くの学生にとって、自分の視野を広げる“きっかけ”になっているようです。 CASE1 国際教養学科×米文学史(英語英米文学科)CASE2 社会福祉学科×マーケティング(心理学科)CASE3 史学科×日本文学史(日本語日本文学科)CASE4 日本語日本文学科×歴史学と民俗学(史学科)
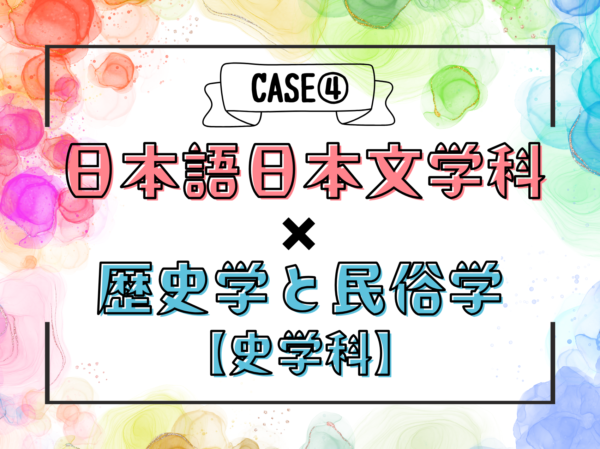
保護者の方にもおすすめ
414
2025.7.25
日本語日本文学科3回生Aさん、Kさん×歴史学と民俗学 神戸女子大学の特徴のひとつに、2024年度から始まった『自分色パレット』(正式名称:テーマ型ユニット)があります。 ※2025年6月取材時 『自分色パレット』とは… 学生が興味をもった「知りたいこと」について、所属する学科以外で開講される講義を受講することができる制度です。自分が所属する学科の講義≒専門分野での学びに加え、所属学科以外の講義から培った知識を合わせることで違った視点でモノを捉え、考える力を養うことができます。 史学科の科目を履修している日本語日本文学科3回生のAさんとKさんに、学びのきっかけや授業の様子についてお話を伺いました。 ——まずは自己紹介をお願いいたします。 Aさん:こんにちは。日本語日本文学科の3回生で、ゼミでは漢字の変遷の勉強をしています。 Kさん:私も日本語日本文学科の3回生で、Aさんと同じゼミで漢字の変遷の勉強をしています! ——お二人とも同じゼミに所属しているのですね!今回お二人とも同じユニット科目を履修されていますが、二人でこれを履修しようと相談されたのですか? Aさん:いえ、それに関しては全くなくって(笑)初回授業の時に初めて一緒のユニット科目を履修していたことに気が付きました。 Kさん:偶然の一致です(笑) ——そうだったのですね(笑)では改めまして、今受けている『自分色パレット』の科目を、履修した理由とともに教えていただけますか? Kさん:はい。私たちはユニット⑦歴史学と民俗学から日本や世界の歴史を探るの「日本民俗学」と「西洋古代中世史」を履修しました。「日本民俗学」は以前この授業を担当している先生の別の授業を受けたことがあって、その時にこの先生面白いから別の授業を受けてみたいなって思ったので受けました。「西洋古代中世史」は高校時代に世界史を習わなかったので、ちょっと知ってみたいなと思って履修しました。 Aさん:私が履修した理由ですが、「日本民俗学」はシラバスに書いてあった“河童”に惹かれて履修しました。また「西洋古代中世史」は高校時代に世界史を習っていたので、もっと深く学びたいなと思って履修しました。 ——なるほど。惹かれるものがあったのですね。実際に授業を受けてみていかがでしょうか? Aさん:どちらの授業もシラバスを見て惹かれて履修したので、自分の思った通りのことが学べてとても満足しています。 Kさん:私も満足しています。特に「日本民俗学」では毎回授業でテーマに沿った歌を歌ってくれるんです!それがとても面白くって(笑) Aさん:あ、確かに歌うよね(笑) Kさん:ね!個人的にはその時間が好きで、和むというか、授業が楽しく感じることのひとつだと思います!(笑) Aさん:そうかも(笑) ——お二人がとても楽しく授業を受けられていることがわかります!授業の中で何か別の学びに結びついたといったことはありますか? Aさん:えっと……。すぐには思いつかないのですが、どちらの科目も自分が所属する学科では絶対に学ぶことができないことを学べています。自分の興味のある科目の知見を深められるのはやっぱり楽しいなと感じます。 Kさん:私もAさんと同じで、自分の知らなかったことや、学科の科目だけでは学べないことを学べるのはすごく楽しいですし、物事の視野が広がった気がします。もし来年度もシラバスを見て、自分の興味が湧いた『自分色パレット』の科目があればぜひ受けてみたいです。 Aさん:うん。そうだね! インタビュー中、終始穏やかな笑みを浮かべていたお二人。そこからは楽しく学んでいる様子が見てとれました。同じ科目でもジブンの学びを描く理由や描いた知識はそれぞれ変わっているようです。『自分色パレット』は、“ジブン色”を探すシンジョ生に送る科目。みなさんも“ジブン色”を探してみませんか? CASE1 国際教養学科×米文学史(英語英米文学科)CASE2 社会福祉学科×マーケティング(心理学科)CASE3 史学科×日本文学史(日本語日本文学科)CASE5 心理学科×認知症の理解Ⅰ(社会福祉学科)
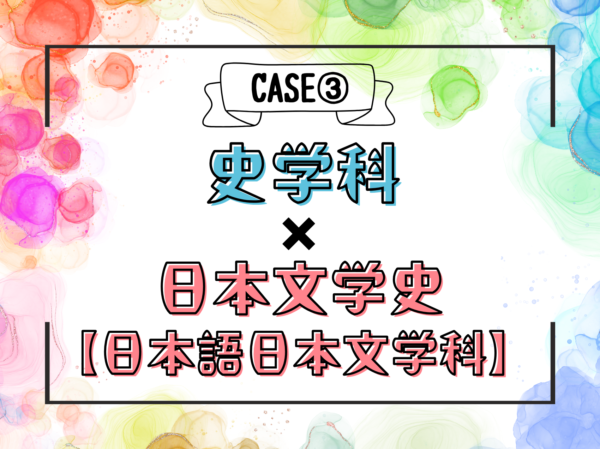
保護者の方にもおすすめ
1260
2024.9.19
神戸女子大学の特徴のひとつに、2024年度から始まった『自分色パレット』(正式名称:テーマ型ユニット)があります。 ※2024年7月取材時 『自分色パレット』とは… 学生が興味をもった「知りたいこと」について、所属する学科以外で開講される講義を受講することができる制度です。自分が所属する学科の講義≒専門分野での学びに加え、所属学科以外の講義から培った知識を合わせることで違った視点でモノを捉え、考える力を養うことができます。 今回はその制度を活用して充実したキャンパスライフを過ごしている史学科Nさんのインタビューを紹介します! CASE3 史学科Nさん(3回生) ×日本文学史 ――自己紹介を兼ねて、入学した理由を教えてください。 私は史学科というざっくり言うと歴史を学ぶ学科に所属しています。高校生のときから将来は文化財に携わる仕事に就きたい!と思っていたので、学芸員資格を取得するために入学しました。 ――『自分色パレット』では何を受講したのか教えてください。 「日本文学史」という日本語日本文学科の講義を受講しました。平安時代の書物や文化に興味があったことが受講した動機です。周囲はもちろん日本語日本文学科の受講生が多いのですが、サークルで知り合った友人と一緒に受講しています。学びとは別の話ですが、友達の友達と知り合うことが出来て交友関係が広がりました。人とコミュニケーションをとることが好きなので、そこも嬉しかったポイントですね! 講義の内容は先生が文学作品のことを次々に解説してくださるのですが、その講義内容が濃密なんです。その作品が生まれた時代背景や流行などの情報もスーッと頭に入ってくるわかりやすい解説で、これまで知らなかった新しい知識がどんどん増えて刺激的でした。また、別の講義にはなりますが、実際に能や狂言を観る機会があったことも印象に残っています。 ――文学作品についての新しい知識を得たことや、「伝統芸能」と言われる能や狂言を実際に観たことで、ご自身にどんな影響がありましたか? 学芸員という職種は博物館の中にいる専門職で、館内の展示品一つひとつを深くまで知っておく必要があります。そのためには現物を観たり触ったり…自分が体験できるものは体験して理解することが大事だと実感しました。あの迫力は文字だけでは表現しきれません! そして、数百年前の史料や文学作品、伝統芸能がこの令和の時代に現存していることを当たり前と思わず、伝統やモノを後世の時代まで残すことを最優先にしてくださった方々に感謝しないといけないと改めて感じました。 これまで自分の中で、博物館へ行った時に綺麗だなとか漠然とすごいな、と思うだけだった部分がありました。今回の学びを経験したことで、作品を作り出した人の思いや、史料の保全や伝統を繋いてきてくださった先人の方々の思いを受け継ぎ、私もまた後世に伝えていきたいという気持ちが強くなりました。 ――素敵な学芸員になって、今後の活躍を楽しみにしています!最後に…自分の将来像はどんな風に描けそうですか? シンジョに入学して成長したと感じることは「何事も体験してみる」という姿勢だと思っています。実は今、今回の文学作品に触れたこともきっかけになって、趣味の範疇ですがちょっとした小説とかを書いてみたりしているんです。他にも…遺跡発掘のアルバイトには募集がかかればチャレンジするようにしていて、その発掘で出てくるような土器やハニワをミニチュアサイズで作って飾ってみたりも。 これからの人生でも新しいことを知って、自分でやってみることでどんどん新しい感覚を身につけて生きていきたいと思っています。何事も前向きに、挑戦する人であり続けたいですね。 その他の自分色パレットの記事はこちら CASE1 国際教養学科×米文学史(英語英米文学科)CASE2 社会福祉学科×マーケティング(心理学科)CASE4 日本語日本文学科×歴史学と民俗学(史学科)CASE5 心理学科×認知症の理解Ⅰ(社会福祉学科)
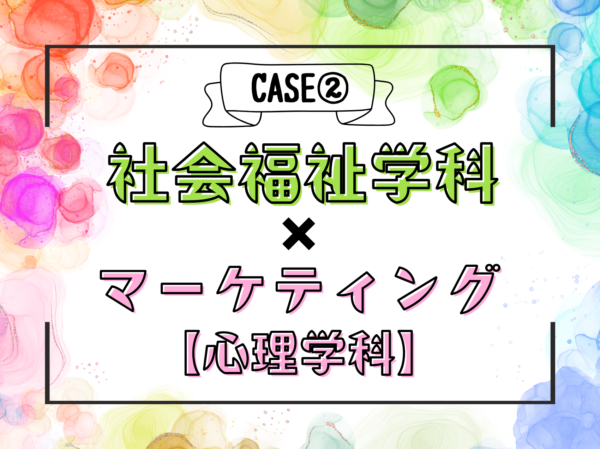
保護者の方にもおすすめ
1060
2024.9.19
神戸女子大学の特徴のひとつに、2024年度から始まった『自分色パレット』(正式名称:テーマ型ユニット)があります。 ※2024年7月取材時 『自分色パレット』とは…学生が興味をもった「知りたいこと」について、所属する学科以外で開講される講義を受講することができる制度です。自分が所属する学科の講義≒専門分野での学びに加え、所属学科以外の講義から培った知識を合わせることで違った視点でモノを捉え、考える力を養うことができます。 今回はその制度を活用して充実したキャンパスライフを過ごしている社会福祉学科Kさんにインタビューを実施しました! CASE2 社会福祉学科Kさん(3回生) ×マーケティング ――自己紹介を兼ねて、入学した理由を教えてください。 私は昔からずっと「人の役に立ちたい」と思っていて、高校生の時に社会福祉というフィールドを知り、これなら人の役に立つ仕事に就けると思って社会福祉学科に入りました。今日は人見知りで緊張しています…よろしくお願いします。 ――『自分色パレット』では何を受講したのか教えてください。 「マーケティング」という心理学科 の講義を受講しました。元々、マーケティングというと「なんとなくこんな意味合いかな」というぐらいの認識だったのですが、これから社会に出て生き抜いていくためにはしっかり理解して身につけておくべき学問だなと思ったので受講しました。 ――先ほどの自己紹介で「人見知り」とありましたが、違う学科の講義を受講することに抵抗はありませんでしたか? やっぱり受講生の大半は自分と違う学科で、講義を担当する先生も今まで関わったことのない先生だったので不安はありました。でも、社会に出るにあたってマーケティング力はやっぱり必要だなと思ったので「自分のためにここは動かないと!」と決心しました。いざ受講してみたら、グループワークがたくさんあったおかげもあって友達もすぐできましたし、先生もすごく気にかけてくれていたので、すぐ馴染むことができて楽しかったです。 ――不安は杞憂に終わったわけですね。社会福祉学科の学びと「マーケティング」を今後にどう活かせそうですか? 実は昨年、所属している社会福祉学科の講義で各種保険制度や保険料について学んだときに「関連した資格を取得できるぐらいやってみよう」と決めて、ファイナンシャル・プランナーという資格を取得しました。 そのことがきっかけになり、就職活動の希望業界が変わったんです。今は自分が育った地元地域に住んでいる方々の生活に対して、お金や保険などの面から役に立つことができる金融業界に興味を持ち就職活動をしています。金融機関の仕事はさまざまな業種の法人や個人の方が顧客になるので、「マーケティング」で学んだことは自分の強みになると思います。 ――「人の役に立ちたい」という考えは変わらず、希望業界が変わったんですね。 「福祉」と聞くと介護を思い浮かべることが多いと思いますが「すべての人が抱える問題や不安を取り除き、生活を豊かにすること」が福祉の本質です。私は金融業界からもその福祉の本質に寄与して「人の役に立つ」ことができると考えています。 ――分野に捉われず色々なことを学べると、自分の可能性が広がっていきますね!最後に…自分の将来像はどんな風に描けそうですか? 私は社会福祉にまつわる実技、法制度だけでなく、人が抱えている本当の問題や本音に触れるために必要なことを学ぶことができました。それに加えて、マーケティングの観点で人やお金の動き、流れを考えることができるようになりました。 自分の将来像としては…うまく一言でまとめられないんですが、どんな場所でも活躍できる「視野が広いかっこいい女性」になっていくと思っています。シンジョで過ごした時間のおかげで自分の考え方がガラッと変わりましたし、自分のことが好きになれました! その他の自分色パレットの記事はこちら CASE1 国際教養学科×米文学史(英語英米文学科)CASE3 史学科×日本文学史(日本語日本文学科)CASE4 日本語日本文学科×歴史学と民俗学(史学科)CASE5 心理学科×認知症の理解Ⅰ(社会福祉学科)
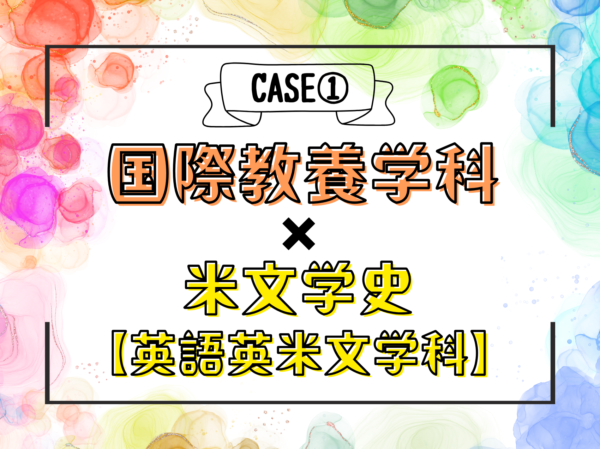
保護者の方にもおすすめ
1065
2024.9.19
神戸女子大学の特徴のひとつに、2024年度から始まった『自分色パレット』(正式名称:テーマ型ユニット)があります。 ※2024年7月取材時 『自分色パレット』とは… 学生が興味をもった「知りたいこと」について、所属する学科以外で開講される講義を受講することができる制度です。自分が所属する学科の講義≒専門分野での学びに加え、所属学科以外の講義から培った知識を合わせることで違った視点でモノを捉え、考える力を養うことができます。 今回はその制度を活用して充実したキャンパスライフを過ごしている国際教養学科のKさんにインタビューした内容を紹介します! CASE1 国際教養学科 Kさん(2回生)× 米文学史 ――自己紹介を兼ねて、入学した理由を教えてください。 私は幼い頃に英会話を習っていたことがきっかけで、海外の歴史・文化に興味をもっていました。高校生のときにK-POPのグループを好きになって、韓国語の授業を受けたりしていて、とにかく海外の色々な国に行って勉強したい!という気持ちが強かったです。シンジョに入学した決め手は留学プログラムの充実具合でした。将来は海外で働くことを目指して、国際教養学科でアジアや欧米の国際情勢や歴史的な背景、語学などを勉強しています。 ――『自分色パレット』では何を受講したのか教えてください。 「米文学史」という英語英米文学科の講義です。アメリカの文学作品や映画を通して、アメリカの歴史的・文化的な背景を詳しく知ることが出来ました。所属している国際教養学科の講義で色々な国の文化や言語を学んできたので、アメリカと諸外国の違いがハッキリ感じられたのですごく充実していました。 ――アメリカとそれ以外のたくさんの国、「世界」を深く学べた訳ですね。 そうですね。講義で知ったアメリカのことは同じ学科の友達に自信をもって話せるぐらいに知識を深めることができましたし、「他の国のことももっと知りたい」と自分の意識も変わりました。世界に、そして日本にも目を向けてアンテナを張って生きることが大切だなと感じるようになり、行動も変わりました。 ――これまでよりも貪欲になった? 色々な国の文化や言語を勉強してきたんですけど、日本でいま起こっていることとか、日本の歴史的なことで知らないことがやっぱりあるんですよね。そう思ったときに「母国のことを知らないのに世界のことなんか学べる訳がない」と思って、自分から知ろうとしなきゃ!と行動が変わりましたね。今は通学時間にニュースアプリで国内外のニュースを見て、調べる習慣が身につきました。調べてもわからないことは大学に着いてから先生に質問したりしています。 ――勉強が楽しくなっている感じがすごく伝わります! 今回、私が受講した「米文学史」は所属している国際教養学科の学びと似ている部分が多くて、学びが繋がった感覚がとてもありました。 でも次は看護学科の講義とか、全然違う分野の講義を受けてみたいなと思っていて。 日本の医療を学ぶことができたら、「じゃあ海外の医療ってどうなんだろう」とまた知りたいことがどんどん増えると思うんです!それをネイティブの先生に聞いてみたり、留学先で聞いてみたり…なんか想像するだけでワクワクしてきます! ――分野に捉われず色々なことを学べると、自分の可能性が広がっていきますね!最後に…自分の将来像はどんな風に描けそうですか? ハッキリとこんな仕事をしたい!というイメージはまだないんです。でも、例えば世界には貧しいといわれているような国もあるので、そのような国が豊かになるために活動してみたいなと思います。そのためには、今学んでいる日本や海外の文化、インフラや政策だけじゃなく「自分色パレット」を活用して、医療であったり福祉であったり…神戸女子大学で学べるたくさんの分野を吸収して、色んな知識の引き出しを持つ人を目指したいです! その他の自分色パレットの記事はこちら CASE2 社会福祉学科×マーケティング(心理学科)CASE3 史学科×日本文学史(日本語日本文学科)CASE4 日本語日本文学科×歴史学と民俗学(史学科)CASE5 心理学科×認知症の理解Ⅰ(社会福祉学科)
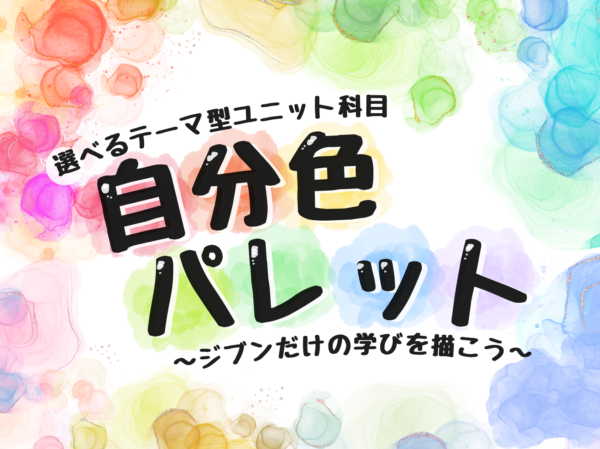
保護者の方にもおすすめ
2246
2023.6.14
幅広い分野で専門的な学問を保有する神戸女子大学。2024年から学生が所属する学部・学科、そしてキャンパスを超えて自由に履修することができる授業『テーマ型ユニット』が始まっています。 今の時代に求められる新しい学習形態、そして女子大学としての役割について紹介します。 『テーマ型ユニット』とは? 神戸女子大学が誇る11の学科が擁する専門性の高い教員陣の授業のうち、全学に開かれたオープン科目(学科や学年を問わず、履修可能な授業)をテーマごとに「ユニット」としてまとめたものです。 履修登録の際には、そのユニットの授業を履修することでどのような能力を身に付けることができるかを明示し、多様な学生に履修後の自分がイメージしやすいようにしています。 ここで、いくつかのユニットを紹介します。※2025年度提供科目 ユニット名 歴史学と民俗学から日本や世界の歴史を探る 「歴史学」の講義では、ヨーロッパの古代・中世史とアジアの近世・近代史のトピックから、現在へのつながりを探ります。また「民俗学」の講義では、日常生活の中から問いを見出し、それを明るく生きがいのあるものにするためにはどうすればよいかを、日本の歴史や文化に即して考えます。(史学科)・日本民俗学・西洋古代中世史・東洋史特殊講義Ⅰ ユニット名 健康と環境の視点から未来のQOLを考える 私たちの未来を考える際、未来における生活の質(QOL)は重要です。しかし、現在も感染症や気候変動など環境は様々な問題に直面しています。地球規模からコミュニティレベルで起こっていることについて理解を深めると共にその解決方法についても授業を通して考えます。(家政学科)・生活環境学・公衆衛生学(管理栄養士養成課程)・食生活論 ユニット名 老化と認知症を理解して超高齢社会にそなえる 超高齢社会になり、多くの人が身近な人の介護を考える時代が来ています。高齢者や認知症のある人について理解し、基本的な介護を大学で学ぶ機会を提供しています。(社会福祉学科)・認知症の理解Ⅰ・発達と老化の理解・介護の基本Ⅰ ユニット名 運動、栄養、健康の観点から人の行動を科学する 人が生きていく上で必要な要素である運動、栄養、健康について、子どもから高齢者までを対象に国際的な視点も加え様々な観点から考察し、最終的には人の行動を科学できる視野を養える科目を提供します。(健康スポーツ栄養学科)・生涯スポーツ科学(スポーツ心理学を含む)・食生活論・国際健康福祉プログラムⅠ(バリ) ユニット名 賢い患者になるためのヘルスリテラシー入門 誰もが医療を受ける機会があり、患者になる可能性があります。賢い患者になるための、医療と法や生命倫理の基礎を学び、治療選択に重要な疫学の知識を身につけることを目指します。(看護学科)・医療と法・生命倫理・疫学 ユニット名 児童・生徒の健康課題を知るために 本学は教職免許を取る学生も多いことから、児童・生徒に起こりやすい健康問題や、在留外国人の健康問題など、教育に関連した健康について学びます。(看護学科)・学校保健Ⅱ・健康相談活動・グローバルヘルスと看護 『テーマ型ユニット』を履修する学生に期待すること。 総合大学である神戸女子大学は、さまざまな学科を設置した大規模なスケールメリットを有する大学として、自由に学習できる環境を整えることで学生たちに学びのきっかけを提供します。学生たちにはそのきっかけを掴み、専門分野にとらわれず、適切な判断力や大局的な視点を身につけることを期待しています。