
特集
560
2025.2.4
"巧妙な手口に惑わされ、焦って支払わないでほしい—"。そんな願いを込め、心理学部心理学科の学生たちが消費者トラブルに関する啓発ステッカーを制作しました。 阪神・淡路大震災から30年を迎えた2025年1月17日、HAT神戸のなぎさ公園で行われた「ひょうご安全の日のつどい・交流ひろば」でこのステッカーを配布した学生たち。防災意識と消費者被害防止を呼びかけた彼女たちの活動の様子をレポートします! 「心理学×社会貢献」プロジェクト このプロジェクトは心理学科の3回生が、兵庫県立消費生活総合センターやNPO法人C・キッズ・ネットワークと連携し、「心理学研究総合演習」の一環として行ったものです。学生たちは消費者心理や詐欺手口について学び、その知識を社会貢献に結びつける形で活動を展開しました。 完成したステッカーのキャッチコピーは、「焦るPay(支払い)が思わぬPain(痛み)に すぐに188にかけよう」。ネットショッピング詐欺や悪質商法はもちろんのこと、トラブルを避けるため、支払いの前によく確認するとともに消費者ホットライン「188(いやや)」の認知度向上を目的としています。 阪神・淡路大震災30年目の想い 2025年は阪神・淡路大震災から30年という節目の年。震災を直接経験していない世代の学生たちですが、被災した家族や地域の方の話を聞き、その教訓を受け継いできました。 今回は消費者被害防止とともに防災意識も高めようと、非常用目隠しポンチョやジッパーバッグなどの防災グッズに啓発ステッカーを貼って配布することに。学生たちは消費生活総合センター職員の方々と協力し、多くの来場者にステッカーが訴える意義と防災意識の重要性を伝えていました。 悪質商法の心理トリックにだまされないで 指導にあたった心理学部の秋山学教授は、「ショッピング詐欺や悪質商法は『残りわずか』『期間限定』などの手法で、消費者に焦りや切迫感を与え、冷静な判断を阻害します」と解説。 昨今、幅広い年齢層がインターネットショッピングを利用するようになったことや、成人年齢が18歳に引き下げられたこともあり、消費者被害は一層身近なものになりました。 例えば、『今だけこの価格!』という格安商品を購入し、代金を支払っても商品が届かないことや、1回限りの購入のつもりが自動的に定期購入になっているなど、巧妙な手口は多岐に渡ります。被害にあった消費者は金銭的にも心理的にも辛い思いをすることになってしまいます。 ステッカー制作の舞台裏 そんな消費者を守るべく、焦燥感にかられた支払いを思いとどまらせてくれるこのステッカー。制作開始から3カ月間、学生たちは試行錯誤を繰り返したと言います。 これまでの学びを総括した結果、①若者世代だけでなく、広い世代に刺さる言葉②「クリックして支払う」行動を止める③キーワードは“焦り”④相談窓口「188」の認知度アップこれら4点をポイントに、短くキャッチーな表現を模索し完成したのが「焦るPay(支払い)が思わぬPain(痛み)に すぐに188にかけよう」です。 デザイン、キャチコピーの提案の様子 プロジェクトメンバーのAさんは、「商品が届かないことや精神的な痛みを“直感的”に想起させる言葉やエフェクトを使ったり、黄・黒・赤といった警告を呼び起こす色を採用したり、細部にまでこだわりました。」と説明。 pain(痛み)にはヒビ割れたようなエフェクトが! 秋山教授とともに学生たちをサポートしてきた同学部の佐伯恵里奈准教授は、「彼女たちの閃きや試行錯誤を見守ってきましたが、視覚的にも響きにもインパクトのあるステッカーに仕上がったと思います。学びと実践が結びついた場面が多く見られ、学生たちにとって貴重な経験になりました。」と語ります。 学んだ心理学が社会で活きる瞬間 学んだ消費者心理を活かし、消費者を守るという実践的なこのプロジェクトを通じて、他人の視点を想像する力を養うことができたと話すAさんは、心理カウンセラーだけではなく、幅広い分野において心理学を活かすことができる可能性を実感しているとのこと。就職活動が始まりますが、「いろいろな場面で強みになる心理学を学んで良かったです。」と笑顔を見せてくれました。 Aさん Yさんは、「心理学科の学生らしく、言葉の伝え方やデザインを工夫した啓発活動ができ、とても充実感が得られました。」と振り返り、今後も積極的に社会課題に関わりたいと語りました。 写真左からYさん、Uさん Uさんはこの活動を通じて、今までより「言葉の伝え方」に興味を持つようになったと言います。「学科の課題や今回のプロジェクトの発表や制作に取り組んできたことで、臨機応変に言葉を使うことができるようになりました。」と話してくれました。 ステッカーで未来を守る 完成したステッカーは、これからも県消費生活総合センターの事業において防災用品や文具などに貼られ、幅広く消費者被害防止の啓発に活用される予定です。 心理学の学びを社会貢献につなげた今回のプロジェクトは、学生たちの成長と同時に、地域社会に希望と安心をもたらす一歩となりました。

特集
886
2024.11.28
みなさん、いきなりですがBE KOBE大学という取り組みをご存知でしょうか?「学校では学べない社会にふれる もうひとつの母校」をキャッチフレーズに、神戸市内の大学生・専門学生が学校や学部の枠を超えて集い、神戸を盛り上げるための活動を行う取り組みです。(主催:BE KOBEミライPROJECT) そんな素敵な取り組みに、心理学科 吉川ゼミの学生がリーダーとなって神戸の老舗パン屋さん「イスズベーカリー」との商品開発プロジェクトを実施。そこで誕生したのが神戸のシンボルであるポートタワーをイメージした、コウベポートタワッフル「コポタワ」です。 2024年10月に開催された「神戸オータムフェスティバル」でコポタワが販売されると聞き、当日にスタッフとして参加したKさん(心理学科2回生)とTさん(心理学科1回生)の2名からこの商品企画がどのように進んできたのかインタビューしました! 写真左から、Tさん(心理学科1回生)、Kさん(心理学科2回生) BE KOBEミライPROJECTとは、市民・行政・企業・大学が連携し、神戸市のシビックプライド・メッセージである「BE KOBE」の実践活動として、神戸の未来を担う子どもたちを支援する取り組みです。―――引用 BE KOBEミライPROJECTについて – より 神戸らしさを詰め込んだ珠玉の“コポタワ”ができるまで 商品開発のために集まった100名以上の学生たち 今回のプロジェクトのはじまりは今年の7月、神戸市内の数々の大学から107名もの学生が集結。これから開発していく商品について、グループごとにアイデア出しをしていきました。 Tさんはまず、この人数の多さに驚かされたといいます。1回生のTさんにとって、周りは他大学の先輩ばかり。そんなグループの中で発言するシチュエーションを想像すると…勇気がいりますよね。その当時のことをTさんに聞いてみると… 「シンジョの心理学科の先輩が1グループに必ず1人ついてファシリテーションするようになっていて、その場の回し方がとても上手だったのでどのグループも積極的な議論ができていました。私自身も意見を出しやすい雰囲気を作ってもらえたので自分の意見をしっかり提案できました。」と話してくれました。 当時の様子を明るく話してくれたTさん 日々の講義でもグループディスカッションの機会が多いシンジョだからこそ、人が活きるグループづくり、そしてグループの中で活きる自分の動きができるのだろうと感じました! "神戸らしさ"を詰め込んだアイデアの数々 グループ間で話し合うときには内容がズレないように、『何が作りたいか』を軸としてアイデアを出し合っていくことに。みんなで話し合って決まった軸は、「"神戸らしさを感じさせるもの"を作り、"神戸のこどもたちを応援するモノ”」に決まります。 ここからは、自由な感性と発想力を持った大学生の独壇場!ぞくぞくとアイデアが湧き出てくる中で、実際に採用されたものはこんなアイデアたち。 神戸のシンボルをモチーフにしたい!→ポートタワーの形を再現!ポートタワーの鉄骨の形はどう再現する?→ワッフルのくぼみがピッタリ!ポートタワーの鮮やかな赤色はパン生地にどうやって着色する?→ベリークロワッサン生地を使用!神戸といえば山→六甲山→六甲山牧場→六甲バター株式会社(本社神戸市)提供の瀬戸内レモンクリームチーズを使用! 学生のこだわりアイデアが詰まったモノが形になりました。 そして、コポタワを1個販売すると、100円をこども支援に募金する「寄付つき商品」として販売することで、神戸の子どもたちを応援することに決定。 神戸らしさを詰め込んだ商品の方向性が決まり、次はプロモーションです! 学生を導く「その道のプロ」は心強い存在 8月にはコポタワのプロモーションについて考えるフェーズに入ります。「流行は若い世代から生み出される」という考えからSNSを中心にプロモーション展開していくことに。実際の投稿内容などを考えていく中で、イラストレーターの井上たつやさんのご協力のおかげでとてもかわいいキャラクターが誕生!その名もコポくん、タワちゃん。SNS展開に必須の魅力的なヴィジュアルが誕生したことでプロモーションも加速していきました。 井上たつやさんのInstagram、HPはコチラInstagramHP コポくん タワちゃん 9月にはコポタワの監修を担うイスズベーカリー本社で試作品試食会が実施されました。まず一口食べた学生から「とっても美味しい!」の声が続々!お味に間違いはないですよ…だってあのイスズベーカリーさんですから!(笑) でも、それだけで終わらないのが学生のすごい所!美味しさを更に引き出すトッピングのアイデアや、販売時にオーブンで焼いてカリッとさせてみてはどうか?という提案も寄せられるなど、更に魅力的な商品を目指してブラッシュアップが行われました。 そんな貪欲な学生たちを導いてくれたイスズベーカリーの井筒社長は、「神戸でがんばっている方々と一緒に活動することで地域を盛り上げることができればと思い、積極的に活動しています。今回のプロジェクトは多くの学生がアイデアを出したおかげで、我々だけではできなかった商品を完成させることができました。参加してくれた学生さんの『これから』につながる機会になればうれしいですね。」と熱く語ってくれました。 写真左からTさん、井筒社長、Kさん 地域活性化にも積極的なイスズベーカリーの情報はコチラから!HPInstagram 想いが込もったコポタワが遂にデビュー。この時のためにやってきた! 7月からの長く濃い道のりを経て、神戸の地で販売されることになるコポタワ。販売ブースではたくさんの学生スタッフがテキパキと準備を行いながら、通りかかる人たちをどんどん呼び込んでいきます。 学生たちの積極性は「自分たちで作りあげた商品を知ってもらいたい!」という熱心な気持ちから生まれるもの。その熱意が伝わったのか、たくさんの人たちがコポタワ販売ブースで足を止めてくれていました。 おそろいのコポくんTシャツを着たスタッフ 自分たちが提案した、提供時にワッフルを温める姿も。 「自分たちが考えた商品なので、『かわいい』という声が聞こえてくるとうれしいですね。色も形も一般的なワッフルらしくないので、『これは何?』と聞かれたりもしましたが(笑)、イスズベーカリーさんとのコラボだと知ると安心して買ってくださるお客様が多かったです。やっぱり昔から地元で愛されている老舗なんだなと実感しました」とKさんは話してくれました。 取材班もコポタワを実食!感想は…本当に美味しい!販売時にオーブンで焼くアイデアが大正解で、表面がカリッと仕上がります。中のもっちりした食感は生地の優しい甘みを引き出し、トッピングのドライフルーツやホワイトチョコの味わいと瀬戸内レモンクリームの爽やかな味の相性がバツグンでした。 本当に美味しかったコポタワ…また食べたいです。 他大学の学生や、社会にふれることで得られたものって? このプロジェクトを通してKさんは、ビジネスにおいて「なんとかなる」という曖昧な考え方では通用しないということを痛感したそう。しかしそこで諦めてしまうのではなく、やりたいことを実現させるために考える続けることを学んだといいます。 そのきっかけは、採算や技術的に実現させることが難しいアイデアを出したときに、井筒社長が頭ごなしに「できない」というのでなく「なぜできないのか」という理由を説明してくださったことで、「じゃあこの部分を修正すれば…!」と思えたそう。 「お店に並んでいるどんな商品も、たくさんの人が関わりながら細かいところまで考えて作られているのだと思うと、これまでとガラッと見え方が変わりました。」と話してくれました。そんなKさんは継続的にBE KOBE大学に参加し、中心メンバーとして活躍しています! イスズベーカリーの井筒社長(写真中央)とKさん(写真右)は実現しなかったアイデアの後日談に花を咲かせていました。 タワーの形も製品化するには相当難しかったそうですが、高い技術力で叶えてくれました! 一方、Tさんは初めて会うメンバーと一緒に作業することが刺激的だったそう。 「プロジェクトには100人以上参加していたので、ミーティングに行くたびに新しい人と出会いました。そのなかで人の意見を聞きながら、自分の考えも聞いてもらえるようなコミュニケーションスキルが鍛えられたと感じています。」 商品開発もプロモーションも、初めてのことばかりでしたが楽しみながら取り組むことができた!と力強く話してくれました。 2025年にはまた新たなプロジェクトが行われる予定ですが、KさんとTさんは「また絶対参加します!」と元気よく話してくれました。そして、この記事を見てくれたみなさんにもメッセージが! 「BE KOBE大学の募集を見かけたら、気軽に参加してくださいね!とても楽しいので、新しい体験がたくさんできると思います!」 「神戸のこどもたちを応援したい」という気持ちを形にしたい。その想いのもとみんなで話し、考え、作り上げたモノが人々を笑顔にしていく光景を間近で見ることができた学生たち。キャンパスだけではできなかったであろう経験を活かし、シンジョ生が次に何を見せてくれるのか…楽しみで仕方ありません! BE KOBE大学の情報はコチラからInstagram

特集
703
2024.10.16
2024年夏、心理学部で経営・消費者心理を中心に学ぶ学生有志が、山陽須磨駅前のシェアキッチン「SUMANOBA」に出店!お店の名前は「1st penguin」(ファーストペンギン)!(7~9月の期間限定出店。現在は営業終了) 今回、最終営業日にスタッフとしてお店を運営していた心理学科3回生のIさんとFさんの2人に、メニュー開発や集客など…実際に出店してみたことでどんな経験ができたのか聞いてみました! Iさん(心理学科3回生) Fさん(心理学科3回生) SNSだけじゃない。やってみたからこそわかる、人とのつながりの大切さ 「ファーストペンギン(以下、愛称であるファッペン)は同じゼミのメンバーで立ち上げた企画なので、企画運営や商品開発に興味のある学生が集まっています。出店が決まってから、まずはお店の方向性を定めるためにマーケティングの授業を参考にしてターゲット層を設定しました。みんなで現地を視察し、アイデアを出し合って『小さい子どもがいる主婦層』にターゲット層を決めたのですが…営業してみると実際の客層は少し違っていました。」とIさん。 「色んなことが想定通りにはいかなかったですね。」とFさんもうなずきます。「集客も思っていた以上に難しかったので、『大学生が営むカフェ』というのぼりを立てたり、お店の前でチラシを配ったりすることで少しずつ周辺の方々に認知されるようになり、お客様が増えていきました。」 他にも、メンバーは大学生である自分たちが得意なSNSを駆使。InstagramなどのSNSでファッペンのアカウントを開設してお店を宣伝し、アカウントをフォローしてくれたら50円引きなどの特典も用意しました。 店内のチラシにはSNSフォロー割の情報が! また、たくさんのフォロワーを持ち、SNS上で影響力のあるインフルエンサーにも声をかけて来店レビューを依頼。10万人以上のフォロワーをもつインスタグラマーが紹介してくれたときは予約がたくさん入り、県外からお越しのお客様がいらっしゃったりと、インターネット・SNSの力を感じたそうです。 ただ、お店を運営してみたからこそ肌で感じたこともあったそうで、Iさんはこう語ります。「SNSをきっかけに来店してくださった方も多いのですが、一度ご来店された方からのクチコミでご新規の方の来店に繋がったことや、オープンが決まった時にご挨拶に回った近隣の方々もたくさんお越しいただいたことで、地域の皆さんに受け入れてもらえているんだと実感できました。 他にも、営業時間終了後に近隣のお店の方にアイスコーヒーを差し入れとして振舞ったことがきっかけで後日来店につながったこともあり、人と直接会って、自分たちで営業活動をすることの大切さを感じることができました。」 メニュー開発、原価計算もこだわって実践。これが本当の社会経験 そんなファッペンで販売している商品は3種のクリームソーダフロート、レモネード、コーヒーやカフェラテのドリンクメニューを中心に、かき氷と看板商品でもあるリボンパンなど。今回取材班がオーダーしたのはレモネード、メロンソーダフロート、ピーチ味のかき氷とリボンパン!見た目も味も最高でした。 レモネード、クリームソーダフロート、ピーチ味のかき氷 さすが女子大生、写真映えする商品を開発! クリームソーダフロートやかき氷にはナタデココが入っています。こちらは神戸市に本社を置く「フジッコ株式会社」から提供いただいた日本唯一の国産ナタデココなんです!見た目、味に加え食感のアクセントも◎ リボンパンはドリンクでセットで購入すると更に写真映えするアイデア商品。こちらは神戸の有名老舗ベーカリー「イスズベーカリー」と共同で開発!もちろん単体でもかわいくておいしかったです。 ドリンクとセットで更にかわいく写真映え こんなにかわいいメニューを自分たちで開発できた経験は楽しかっただろうと思っていると、Fさんがメニュー開発で印象深かったことを話してくれました。 メニュー開発での出来事を教えてくれたFさん 「最初はバズる商品を作るとか、かわいいメニューを作ろう!という気持ちでメニューを考案したり試作に臨みましたが、ゼミの吉川先生のご紹介でスイーツのヒットメーカーの方にアドバイスをいただいたんです。 その内容は『店舗を営業し続ける、つまり経営していくためには、利益を出すための原価計算(注1)が不可欠』であるということ。(注1)商品を完成させるために必要な材料の分量や金額を算出すること。今回は主にシロップや炭酸水の分量など。 そして、『利益を出せるように算出した原価分の分量を守るため、オーダーが通ったら目分量でドリンクを作るのではなく、当たり前のことだけど計量しながら作らないといけない。』とアドバイスをいただきました。」 忙しくてもしっかり計量して提供! 「もちろんそれまでも真面目に取り組んでいましたが、おいしさやかわいさ以外に『利益』を出すために大事にしなければならないことがあると学びました。メンバーみんなで味見と計量を繰り返しながらメニュー開発をしたことは大変でしたがとても楽しかった思い出です。」 Iさんも、「授業でも原価や利益について考えることはよくありますが、実際に自分がお店に立ってみると思っていた通りにはいかないこともありました。例えば…しっかり計量して商品を提供しなければならないけど、目の前にはとても急いでいる様子のお客様が待っている時や、利益を出すために必要な一日の売り上げ目標に届かなかった日もあったり。 でも、想定外のことをたくさん経験したことで、この先に起こりそうなことを予想して『ここまで準備しておこう』と考えたり、その場で対応できる力を養うことができたと思います。」と前向きに話してくれました。 複数のオーダーを段取りよく、そして見栄えよく提供してくれたIさん 貴重な経験を通して身についた「〇〇力」を聞いてみた! 最後に、今回のファッペンでの経験を振り返って自分自身がどんな力が身についたと思うか聞いてみました。 Iさんは「行動力」とのこと。「やってみたい!おもしろそう!という思いで、いい意味で深く考えすぎずに始動したファッペンでしたが、みんなで力を合わせることでなんとかやり遂げることができました。 実際にお店を出店するというだけでも大きなことだと思っていたのですが、たくさんの人との出会いもあってグラングリーン大阪に出店するチャンス(のちに9月28日限定で出店)も頂けました。 行動してみたことで、私たちだけしか経験できないことができて、その次の展開や新しい人脈が広がっていく体験ができました。 『やればできる』を体感したことで、プライベートでも興味をもったところにすぐ足を運んだり、積極的に行動するようになったと感じています。」 そしてFさんは「問題解決力」。「この2か月の営業期間中は何度も壁にぶつかりましたが、悩んだときは一人で抱え込むのではなく声に出してみんなに伝えることが大切だと実感しました。 そうすることで問題に対してみんなの目線を合わせ、一致団結して問題解決に向けて動くことができました。ひとつひとつ問題を解決していったことで、目に見えてスムーズに営業できるようになっていきました。」 最後になりましたが、店名にもなっている「ファーストペンギン」という言葉の意味をご存知でしょうか?氷上で過ごすペンギンの群れの中から、エサとなる魚を求めて海に飛びこむ最初のペンギンのように『リスクを恐れずに挑戦する人』を表す言葉なんです。 この夏、チャンスを掴みに飛び込んでいった彼女たちは貴重な経験を経て大きく成長することができました。シンジョの『ファーストペンギン』の今後の活躍も見逃せません!
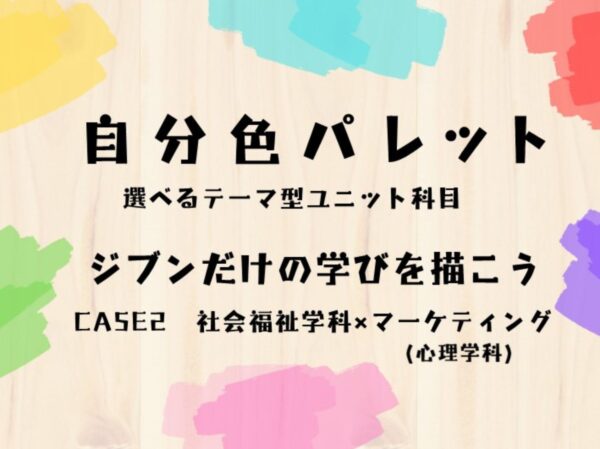
保護者の方にもおすすめ
722
2024.9.19
神戸女子大学の特徴のひとつに、2024年度から始まった『自分色パレット』(正式名称:テーマ型ユニット)があります。 『自分色パレット』とは…学生が興味をもった「知りたいこと」について、所属する学科以外で開講される講義を受講することができる制度です。自分が所属する学科の講義≒専門分野での学びに加え、所属学科以外の講義から培った知識を合わせることで違った視点でモノを捉え、考える力を養うことができます。 今回はその制度を活用して充実したキャンパスライフを過ごしている社会福祉学科Kさんにインタビューを実施しました! CASE2 社会福祉学科Kさん(3回生) ×マーケティング ――自己紹介を兼ねて、入学した理由を教えてください。 私は昔からずっと「人の役に立ちたい」と思っていて、高校生の時に社会福祉というフィールドを知り、これなら人の役に立つ仕事に就けると思って社会福祉学科に入りました。今日は人見知りで緊張しています…よろしくお願いします。 ――『自分色パレット』では何を受講したのか教えてください。 「マーケティング」という心理学科 の講義を受講しました。元々、マーケティングというと「なんとなくこんな意味合いかな」というぐらいの認識だったのですが、これから社会に出て生き抜いていくためにはしっかり理解して身につけておくべき学問だなと思ったので受講しました。 ――先ほどの自己紹介で「人見知り」とありましたが、違う学科の講義を受講することに抵抗はありませんでしたか? やっぱり受講生の大半は自分と違う学科で、講義を担当する先生も今まで関わったことのない先生だったので不安はありました。でも、社会に出るにあたってマーケティング力はやっぱり必要だなと思ったので「自分のためにここは動かないと!」と決心しました。いざ受講してみたら、グループワークがたくさんあったおかげもあって友達もすぐできましたし、先生もすごく気にかけてくれていたので、すぐ馴染むことができて楽しかったです。 ――不安は杞憂に終わったわけですね。社会福祉学科の学びと「マーケティング」を今後にどう活かせそうですか? 実は昨年、所属している社会福祉学科の講義で各種保険制度や保険料について学んだときに「関連した資格を取得できるぐらいやってみよう」と決めて、ファイナンシャル・プランナーという資格を取得しました。 そのことがきっかけになり、就職活動の希望業界が変わったんです。今は自分が育った地元地域に住んでいる方々の生活に対して、お金や保険などの面から役に立つことができる金融業界に興味を持ち就職活動をしています。金融機関の仕事はさまざまな業種の法人や個人の方が顧客になるので、「マーケティング」で学んだことは自分の強みになると思います。 ――「人の役に立ちたい」という考えは変わらず、希望業界が変わったんですね。 「福祉」と聞くと介護を思い浮かべることが多いと思いますが「すべての人が抱える問題や不安を取り除き、生活を豊かにすること」が福祉の本質です。私は金融業界からもその福祉の本質に寄与して「人の役に立つ」ことができると考えています。 ――分野に捉われず色々なことを学べると、自分の可能性が広がっていきますね!最後に…自分の将来像はどんな風に描けそうですか? 私は社会福祉にまつわる実技、法制度だけでなく、人が抱えている本当の問題や本音に触れるために必要なことを学ぶことができました。それに加えて、マーケティングの観点で人やお金の動き、流れを考えることができるようになりました。 自分の将来像としては…うまく一言でまとめられないんですが、どんな場所でも活躍できる「視野が広いかっこいい女性」になっていくと思っています。シンジョで過ごした時間のおかげで自分の考え方がガラッと変わりましたし、自分のことが好きになれました! その他の自分色パレットの記事はこちら CASE1 国際教養学科×米文学史(英語英米文学科)CASE3 史学科×日本文学史(日本語日本文学科)

特集
1895
2023.12.14
さまざまな企業と産学連携の取り組みを行っている神戸女子大学。今回タッグを組むのは、「フジッコのおま~めさん」のフレーズでお馴染み、自然の恵みを大切にしながら商品開発を続けるフジッコ株式会社。(本社:神戸市) 同社の看板商品である「おまめさん きんとき」は、つややかできれいな見栄えが求められるため、生産工程で出る皮の破れた豆は製品に使用せず食品ロスが発生していました。 しかし、この豆は皮が破れているだけで品質には問題がなく、おいしさは同じです。何とかして価値あるものに生まれ変わらせることはできないか…。 そしてもう一点、若者の豆離れにも一石を投じることができれば!ということを考え、『Z世代がZ世代のために考えた ちょっと高くてもついつい食べたくなる豆アイスの商品企画』がスタートしました。ちなみに、この特別講義は「教養演習1」という講義。学部学科の垣根を越えて、さまざまな学生が受講しています。 今回は、学生がこれまでの講義を踏まえて企画したオリジナル豆アイスを、フジッコ株式会社の役員や各部署の部長職など錚々たる面々にプレゼンする中間発表の日を取材しました! 看板商品である おまめさん きんとき 役員、各部署長の皆様もお越しくださいました。 各講義は「講座」「活用例」「実践」の3ステップ力をつけながら商品企画を行う 産学連携で行われるこの商品企画プロジェクトは、全13回にわたります。本格的なマーケティングの知識と商品企画について、現場の第一線で活躍されているフジッコ株式会社の只野さんから直接ご指導いただき、学生ならではのアイデアで新しいアイスを企画。最終的なゴールである商品化を目指し、グループのメンバーと協働して商品企画を中心にターゲットの具体化、販売チャネル、プロモーションなどについて考えていきます。 1回の講義の中では、まずはマーケティング論など座学部分を講義形式で学び、その活用例として実務でどのように採り入れているか教えていただきます。その後、グループワーク形式で、その日に学んだことを活かしながら少しずつ商品企画を進めます。 この講義構成について、学生はこう話します。「只野さんがこの講義のために時間を割いて丁寧に準備をしてくださっていることが至る所で感じられます。ここまで私達のためにわかりやすく、そして力がつくように準備してくださっていることに感謝するとともに、絶対に良い商品を作りたいと思っています。」 現場のプロから見たシンジョ生。感性と吸収力に期待! これまで学生に、現場で使う本格的な知識や技術をわかりやすくご教授いただいている、フジッコ株式会社の只野さんに神戸女子大学の学生の印象をお聞きしました。 「ワークシートの記入など、目の前のやらなければいけないことに対し、常に一生懸命ですね。そのため講義内容の飲み込みが早く、教えたことをすぐに自分のものにしていると思います。また、グループワークで活発に話し合う姿が印象的でした。友達同士では明るく話せる子も、グループワークになると黙ってしまうことがよくありますが、それがありませんね。」と只野さん。 講義中の様子 グループワークの活発さは、普段の講義からグループワークを積極的に行っている神戸女子大学の特徴そのもの。それに加え、女子大だからこそ、女性同士でのびのびと積極的に取り組めているのかもしれません! 他にも只野さんは「神戸女子大学の学生のみなさんは感性が素晴らしいと思います。はじめは商品の価値(商品を通じてもたらされる嬉しい期待)を考えることに苦戦していた様子でしたが、具体的な生活シーンを想像しながら「元気にしてくれる豆アイス」「癒される豆アイス」「ほっと落ち着ける豆アイス」「楽しいが増える豆アイス」など、さまざまな意見を出してくれます。どうしても大人は理屈っぽい考えが多くなりがちですが、今日の発表にも『Z世代の彼女たちらしさ』が存分に発揮されています。」と仰ってくださいました。 うちの企画部でも通用するかも!とお褒めいただきました これまでの集大成!想いをぶつける中間発表。 今回の発表内容は、販売ターゲットを絞り込んで具体化する「セグメンテーションとペルソナ設定」、提案する豆アイスを食べるのにぴったりな場面、生活の中での豆アイスの位置づけ、試作品から製品にするための改良点などをまとめた「商品企画コンセプト」、豆アイスがもたらす嬉しい期待とそれを実現する品質との関係をまとめた「ブランドエクイティピラミッド」など。4つのグループがそれぞれ特色ある考えを発表し、それに対して質疑応答を行いました。 ●Aグループターゲット:部活や仕事に日々全力で取り組むZ世代アイスの役割:疲れた時のご褒美、癒して元気にしてくれる提案アイス:『きんとき豆うさぎ』(想定価格250円) きんとき豆が持つ甘味を活かした『きんとき豆うさぎ』。今後、元気を象徴する豆うさぎをデザインに施すそう。 「ライバル商品に勝つための強みは?」という質問に対し「豆が持つ食物繊維をはじめとした栄養素が取れること」と回答するAグループ ●Bグループターゲット:一人暮らしで孤独を感じている女子大生役割:一日の終わりに癒しを与える試作アイス:甘えたくても甘えられない夜に癒しを与えるアイス(想定価格:300円) アイスのイメージはツンデレ彼氏。滑らかな舌触りでやさしい甘さのきんときアイスとナッツの食感でツンデレを表現。 自分たちの体験をもとに、説得力のある発表を行うBグループ 試作品はみんなで試食! ●Cグループターゲット:映える場所や物を求める、SNSを中心に生活する女子大生アイスの役割:SNSに振り回され疲れたところを癒す試作アイス:自分自身と向き合う時間を作るアイス(想定価格:300円) きんとき豆と抹茶を組み合わせ、和の香りで心が落ち着くように。豆が苦手な人でも食べられる豆アイスに。 どういった状況でこの商品が選ばれるのか、図を用いてわかりやすく説明 アイスを「遠方に住んでいる優しいおばあちゃん」と表現し発表するCグループの皆さん ●Dグループターゲット:大人数で初対面の人とでも仲良くしたいZ世代アイスの役割:会話を生み、盛り上げる遊びのツールとして提案アイス:食べて楽しいが増えるアイス(想定価格700円※ファミリーパック1箱) ミルクきんとき味のアイスのまわりをチョコでコーティング。個包装のパッケージにクイズやゲームなど、大人数で楽しめる要素をつける予定。 類似商品を使用し視覚的にイメージを伝えるDグループ 「本気でヒット商品を作りたい」という想いを伝えるべく奮闘した学生たち。それに応えるようにフジッコ株式会社の皆様も真剣に質問を投げかけます。 「滑らかな食感を出すために豆の食感を感じさせないようにしたい」と発表をしたグループに対し、「豆アイスである必要があるのか?」という鋭い質問も。 それに対して、自分達の感性を活かしてその場で「粒あんが苦手でも、こしあんだったら食べることができる人も身の回りにいます。実は私も豆の皮の食感が少し苦手です。だから、豆の風味や味わいを残しながら食感を滑らかにすることで、よりたくさんのZ世代に寄り添える商品になるとイメージしています。」と答えた学生には、社員の方も納得の表情。 その道のプロの考えや空気感にも触れられたこの中間発表は、学生たちを大きく成長させたに違いありません! 山場をひとつ乗り切った学生たちにこの産学連携の魅力を聞いてみた 今回Cグループとして発表していた、心理学部心理学科2年のEさんとIさんにこの講義の魅力を聞きました。 ――この講義の魅力を教えてください。 左:Eさん 右:Iさん Eさん「学生のうちから商品企画に携われることはなかなかありません。自分たちが真剣に考えたものが、店頭で売り出されることになれば、かけがえのない経験になると思います。また、特別講師の只野さんが『学生だから』という甘い対応ではなく、一緒に商品企画をするメンバーの一人として接してくださっているのが非常に嬉しいです!」 Iさん「この講義では、主体的に動くかどうかで、得られる経験が大きく変わってくると感じています。そのような状況を理解しながら学んでいるので、課題に対してより細かく、具体的に考える習慣がつき、自分達の力になってきていると思います。」 前向きに取り組み、回数を重ねるごとに力をつけていく学生は、今回の試作アイスをどのようにブラッシュアップしていくのでしょうか。12月20日には企画する商品の最終プレゼンテーションも控えているそう。みなさんの身の回りのお店で、学生が企画した豆アイスが見られる日はそう遠くないかもしれません!

特集
1170
2023.12.6
神戸女子大学では、現場の専門知識を持つ方を学外からお招きし、現場の空気感に触れられるような特別講義を数多く実施しています。 今回は心理学科の『産業組織心理学』の講義にTOPPAN株式会社とネスレ日本株式会社から講師をお招きした特別講義を取材。「ミライーね!出張授業inシンジョ」と題するこの講義では、身の回りにある『社会課題』を両社の『共創』によって解決している取り組み事例から、産業組織心理学について学びました。 ●過去の特別講義はこちらから神戸女子大学の学びは現場で活きる!特別講師による『教養演習』を取材してみた!(川崎重工業様)【神戸女子大学×資生堂】シンジョの心理学科がまるわかり!特別講義を独占取材 ●「ミライーね!」とはTOPPAN株式会社が推進する、「企業」と「教育現場」をつなぎ、さまざまな企業のサステナブルな取り組みを楽しく、分かりやすく伝える「学び」と「体験」の場を提供する取り組み。様々な企業との共創活動を通じて、未来に「いいね!」を提供します。 YouTubeチャンネル「ミライーね!チャンネル」はこちらから 『産業組織心理学』とは? 心理学が組織のパフォーマンスを左右する そもそも『産業組織心理学』とはどのような学問なのでしょうか。まずはそれを簡単にご紹介します。 【産業組織心理学とは…】・心理学的観点から、組織における個人の行動や心理を理解し、マネジメントや人事施策に役立てる学問・組織のパフォーマンスを向上させるために、メンバーの能力やモチベーションを最大限に引き出すための手法や理論を学ぶ 人生の中で少なくない「就業時間」を心理学の観点からより良いものにするために学ぶことができるこの学問は、面接や人事評価、就職活動で用いられる適性検査にも活かされているほど! まさに『なんだ、こころ なんだ』をキャッチフレーズにする『シンジョ心理』らしい講義です。 講義内容を少しだけご紹介! 『産業組織心理学』の特別講義 今回の特別講義では持続可能な社会の実現と企業価値の向上に取り組む「社会的価値創造企業」としてTOPPAN株式会社と、「ネスカフェ」や「キットカット」をはじめとした、誰もが知る超人気商品の開発・製造・販売を行い、「食の持つ力で、現在そしてこれからの世代のすべての人々の生活の質を高めていきます」という存在意義(パーパス)を掲げているネスレ日本株式会社の事業紹介からスタート。 その後、両社の共創が生んだ取り組み事例から産業組織心理学について学びます。 講義はリアルタイムアンケートで学生の生の声を拾いながら進行。 学生の理解度や質問が随時画面に表示されます。 本講義のテーマは「社会課題解決視点×共創」。進行のTOPPAN株式会社の山田様は「地球温暖化や高齢化をはじめとした社会課題に立ち向かうことは、企業の大事な責任のひとつ」と語ります。 しかし、環境問題などの大きな社会課題に立ち向かうには1社だけではなく、複数の企業がそれぞれの知見や技術を持ち寄り、『共創』することが必要になります。TOPPAN株式会社とネスレ日本株式会社はこれまでもさまざまなシーンで共創した取り組みを実施しています。 まずは、両社の共創によって実現したサステナブルな取り組みをご紹介します。近年、環境への配慮のため、さまざまな企業や場面でビニール袋やストローなどのプラスチック素材のものが廃止されています。実は、ネスレ日本株式会社の有名な商品の「キットカット」も、環境に配慮した紙パッケージに生まれ変わるべく、同社から相談を受けたTOPPAN株式会社が総力をあげて開発! 従来のプラスチック製の外袋の特徴でもある高い耐久性、パッケージへの印刷の自由度に近づけた紙パッケージを開発し、現在の形で販売されています。外袋素材が紙になった「キットカット」はカカオ感やウェハースのサクサク感もリニューアルされ、「史上最高」と大きく印刷されたパッケージが目印。店頭で見かけたら是非、紙パッケージの手触りと史上最高のおいしさを確かめてみてくださいね。 取組内容をわかりやすく説明してくださったネスレ日本株式会社 的場様 そして、両社の共創が生んだ数ある取り組みの中でも、『産業組織心理学』として私達が注目したものは、「ネスカフェ パパママカフェ」。この取り組みは、幼稚園、保育園に関連する人々のコミュニケーションを円滑にし、社会課題を解決していったものです。 近年、社会環境やライフスタイルの変化により地域コミュニティの数が減少し、保護者、幼稚園の先生、保育士さんがコミュニケーションを取る場や悩みの相談ができる機会が少なくなっていると言われます。そこで、TOPPANのグループ企業で、児童書などの販売を行う株式会社フレーベル館が監修し、幼稚園や保育園の一角にスペースを提供。そこにはネスレ日本株式会社が誇るお菓子や「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」を設置し、保育士と保護者、保護者同士が集まる「パパママカフェ」を創りました。それにより、幼稚園、保育園に関わる人々のコミュニケーションの場や気軽に相談ができる環境を生みだすことに成功し、社会課題解決に貢献しています。 まさに、この両社だからこそできた共創による「ミライーね!」な取り組み! このように企業が経済活動を行うだけではなく、社会課題の解決に向けて取り組んでいることや、社会課題を見つける目とそれを解決するアイデアを持つ企業人に向けて、目を輝かせながら受講していた学生の姿が印象的でした。 『産業組織心理学』―特別講義を終えた受講学生の声― ――講義の感想を教えてください。 これまで学んでいた『産業組織心理学』が実際に社会でどのように活かされているかを知り、一段と理解が深まりました。また、企業様の具体的な取り組み事例を伺えたことで、今後私が受講しようと思っているボランティアを企画し実施する講義で、どのように実践すれば地域の方に喜んでもらえるか、というヒントを得ることもできました。今回の授業で得られたものは大きく、とても充実した時間だったと思います。 受講中の様子 本学では、これからも学生が興味を持ち、自ら参加したくなるような有意義な講義をたくさん準備しています。 次回の特別講義もお楽しみに!

カルチャー
1354
2023.10.18
2023年8月、神戸市・三宮にある三宮本通商店街と三宮センターサウス一帯を併せたミチニワエリアで、「ミチニワ meet up! 夏あそび2023」が開催されました。このイベントで19日に行われた「ゆかた de ストリートスナップ」という企画を運営したのは、なんと神戸女子大学の心理学科1回生。今回はその活動に密着しました。 ミチニワを盛り上げたい組合とのつながり 「ミチニワ」という愛称は、2022年11月と翌年1月に開催された三宮本通商店街 と三宮センターサウス通の合同イベント、「テロワール市」で築かれた地域のつながりの維持・発展を目的に命名。3月にはこれを記念し、町開きイベントも開催されました。 地域連携による学びを積極的に取り入れる神戸女子大学は、心理学科の講義でミチニワ誕生以前から三宮本通商店街の活性化に尽力しており、テロワール市と町開きイベントにも協力しています。 これまでの主な活動は、若者視点からのSNS運用やイベント当日の運営でしたが、今回の「ミチニワ meet up! 夏あそび2023」では、それらに加えてコンテンツの企画にも参加。3月から月に2度ほど打ち合わせも行い、この日を迎えました。 三宮本通商店街振興組合の代表理事・高井様は神戸女子大学の学生について、「皆さんコミュニケーション能力が高く、主体的な印象です。打ち合わせでは『こんな企画どう思う?』と聞くと、遠慮することなく素直に意見をぶつけてくれます。私たちにはなんてことのない昔からある喫茶店ひとつにしても『このようなレトロ喫茶はウケる』と、私たちにはない着眼点と発想で新たな提案を持ちかけてくれるので、特に若者層をターゲットにした取り組みには欠かせません」と話してくださいました。 学生の活躍がこの日の盛況を左右⁉プログラムからわかる学生の重要度。 「ミチニワ meet up! 夏あそび2023」は、以前にも特別講義をしてくださった川崎重工業株式会社の開発アプリ、Real D You(リアデュー)を用いたプレゼント企画「ミチニワで遊ぼう まち歩きキャンペーン」や「ミチニワ夏あそび フォトコンテスト」、学生が担当する「ゆかた de ストリートスナップ」、その翌日開催の「舞妓さんのミチニワ散歩」と「ほこみち JAZZ LIVE」など、常にさまざまな企画が実施されていました。 ●川崎重工業株式会社による特別講義の様子はこちらから https://nyushi.kobe-wu.ac.jp/mag/parents/article-5570/ オリジナルコーヒーの試飲、販売をする期間限定ショップも開店。 神戸市内で人気のスイーツ店のポップアップショップも。 「#ミチニワで遊ぼう まち歩きキャンペーン」と「ミチニワ夏あそび フォトコンテスト」はイベント開催中絶えず実施しているため、19日の盛り上がりは「ゆかた de ストリートスナップ」次第! この企画は道行く人に声をかけ、Instagramで人気のフォトグラファーYuma Takatsukiさんによるストリートスナップ撮影に協力してもらうというもの。撮影後はその場でチェキを手渡し、後日ミチニワの公式Instagramでその活動を投稿して、ミチニワの盛り上がりをアピールします。 学びが活きた!声かけに「心理学」をフル活用! 一日の流れについて打ち合わせをし、いざ商店街へ。ストリートスナップの撮影に協力してくれる人を探します。 物怖じすることなくどんどん声をかけていくシンジョ生。 自分たちが持つインスタントカメラ「チェキ」でもしっかり撮影。 シンジョ生が提案したチェキの配布は大好評! 今回密着していた間、ほとんどの方が快く撮影に協力してくださっていました。そこにはなにか秘密があるのでしょうか。少しお話を聞いてみました! ― この講義を選択した理由を教えてください。 S.Mさん「昔からボランティアに興味があり、この講義なら学びの中で地域貢献ができると思ったからです。私は愛媛から来たのですが、この講義を通して神戸に愛着が持てることや、人と触れ合うことで社交性が身につくことも大きな魅力だと思います。」 M.Mさん「高校生の時に興味を持ったマーケティングを本格的に学びたいと思い選択しました。実際に体を動かして学べるので、学んだことが身につきやすいと感じています。」 積極的に声をかけるS.Mさん(右から2番目) ― 声をかける際に意識したことは? M.Mさん「1組協力を得てからは、その様子を見ていた人に声を掛けました。これは『じゃあ、私も』という集団心理、バンドワゴン効果を狙ったものです。」 N.Yさん「私は初対面の方と距離を縮めるために、『出身地はどこですか?』など、答えが『はい』か『いいえ』の2択にならない質問をしていました。今回の活動はこれまでに学んだ心理学を試すにはぴったりだったと思います。」 左から心理学科のN.YさんとM.Mさん。 いつも素敵な笑顔のおふたり。 神戸女子大学では活きた専門知識や技術を、楽しみながら身につけられる地域学習を数多く用意しています。 ミチニワの活性化に挑む三宮本通商店街振興組合への協力は今年で2年目。すでに次回イベントの企画も進んでいるようなので、これからも神戸女子大学の地域活性化、そしてミチニワの発展から目が離せません!

神女サポート
1397
2023.8.25
2023年8月5日、神戸・ポートアイランド市民広場で開催された「ポートアイランド夏祭り2023」に神女ポーアイボランティアセンターが参加しました。地域のイベントを盛り上げるために奮闘したメンバーの様子をお届けします。 地域とつながる、神女ポーアイボランティアセンター 神女ポーアイボランティアセンター(以下、ボラセン)とは、2022年5月、神戸女子大学ポートアイランドキャンパスに設立された団体。発起人である社会福祉学科3回生のKさんを中心に、学生が主体となって運営しています。 ●ボラセン設立についてのインタビュー記事はこちら 立ち上げから1年以上経った現在、メンバーは倍以上の20名程まで増え、活動の幅も拡大。他のボランティア団体が運営する既存企画に参加するだけではなく、自らイベントを企画・実施することも増えています。 例えば先日、ポートアイランドキャンパスにて「タイダイ染めリメイクイベント」を開催。地元自治会である港島自治連合協議会の掲示板で告知いただいた効果もあり、当日は周辺にお住いの多くの方が参加くださったのだとか。3歳から70代まで幅広い世代の交流の場となりました。 地域のイベントにボランティアとして参加したり、自分たちが企画したイベントに地域の方を招いたり。今や地域とのつながり創出も、ボラセンの大切な活動テーマの一つとなっているのです。 4年ぶりに復活! 住民待望の夏祭りにボラセン初参戦!! そして2023年8月5日にポートアイランド市民広場で行われた「ポートアイランド夏祭り2023」に初参加。 夏祭りは、港島自治連合協議会が主催する毎年の恒例行事です。地域に関わる企業や団体、住民による組合などが集まって計20以上の屋台を出店し、中央ではコンサートや盆踊りを実施。例年5千人程の来場者が訪れるという、地域の一大イベントとなっています。 実は昨年も夏祭りに参加すべく準備を進めていたボラセン。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大のため開催数日前に中止が決まり、残念な思いをしていました。結果的に夏祭りは2019年から4年連続中止となり、今年ようやく開催できることに。例年以上の盛り上がりが期待される中、満を持して挑みます! 4年ぶりの開催に向けて準備が進む会場。すでに活気に溢れています。 映え間違いなし☆ 3色わたあめで勝負 ボラセンは、昨年予定にしていた綿菓子の屋台を出店。3色の綿菓子をカップに重ねた「ゆめかわ わたあめ」を販売します。 メンバー皆で考案した、映える「ゆめかわ わたあめ」 事前にSNSでの告知など分担して準備を行い、当日は9名のメンバーが売り子として参加。ボラセンのシンボル、お揃いのTシャツを着てお店に立ちます。 ボラセン屋台、準備万端! ちなみに、このTシャツ制作費もお店の運営費も、すべて神戸女子大学独自の学生課外活動助成金制度「神女support」を利用して資金調達。おかげで費用の心配をすることなく、幅広い活動ができているのです。 綿菓子機械のレンタル費、材料の購入費などに「神女support」をフル活用。 いよいよ17時にお祭りがスタート。ボラセンの屋台「ゆめかわ わたあめ」はそのかわいらしさから、あっという間に行列ができていきなり大忙しです。 特に小さなお子さんや女子学生に大人気。 開店直後から大盛況。 一緒に販売している「チェキ撮影サービス」も好評です。 思い出に残る1枚を撮影。 めっちゃ暑い&忙しいのに、笑顔を絶やさない素敵なメンバーたち。 気づけばこのにぎわい! 夜にかけてまだまだ来場者は増える一方です。 メンバー一同フル稼働! 呼び込みも待ち列整理も大変! 地域とボラセンのつながりは、より強くより深く 夏祭りのにぎわいづくりに一役買ったボラセン。代表の社会福祉学科3回生のKさんはこう話します。 「この1年間、地域の皆さんと関わる機会を多く持てて、交流が深まっていると感じます。今日もわたあめ屋台を通してたくさんの地域の方と触れ合えました。中には先日のタイダイ染めイベントの参加者の方もいて、気さくに声をかけていただけて嬉しかったです」。 来店者と積極的にコミュニケーションをとるKさん。 こうした地域との関わりにおいて欠かせないのが、夏祭りをはじめ多くの地域イベントを主催する港島自治連合協議会の存在。 Kさんは「自治会の方々はいつも優しくしてくださる一方、私たちがより良い組織になるようきちんと意見や提案もしてくださるので有難いです。しっかりと信頼関係ができていると感じます」と言います。 今後も地域と密接に関わっていきたいというKさん。「特に、幅広い世代が参加できるイベントを企画していきたいと考えています。そこで、子どもとお母さん・お父さん、そしておばあちゃん・おじいちゃん世代がつながるきっかけが生まれれば良いなと。私たちが地域の世代間をつなぐネットワークになっていきたいと思っています」。 「また秋にも地域のイベントに参加する予定です」とKさん。まだまだ勢いは止まりません! 一方、港島自治連合協議会の事務局長・粟原富夫さんも、「神戸女子大学とはポートアイランドキャンパスができて以降、地域イベントへの参加などを通して交流がありましたが、ボラセンができてからはより連携がしやすくなりました。交流の機会がぐっと増えて、つながりがどんどん強くなっています」と話します。 ボラセンと地域をつないでくださっている粟原さん。 そして、今後の活動にも大いに期待されている様子。「学生さんたちにはどんどん地域に入ってきてもらいたいです。特に港島エリアは年々、住民の高齢化が課題になっています。そこで例えば、看護や福祉、健康、栄養などを学ぶ学生さんたちが、地域のお年寄りを対象に学びの内容を実践してくださるなど、大学の研究内容が地域に還元されるような取り組みにも期待しています」。 お祭りの終盤、各団体のPRタイムが設けられた際も、ボラセンは地域の方々に向けて自分たちの活動内容や熱い思いをアピール。最後は元気よく「皆さんで協力してポートアイランドを盛り上げていきましょう!」と締めくくると、大きな拍手と歓声が沸き起こりました。 櫓の上からしっかりとアピール! ラストは盆踊りの輪にも参加♪ 屋台の行列は閉店まで続きました。 夏祭りをきっかけに、また一歩前進したボラセンの地域貢献活動。今後の活躍から目が離せません!ぜひ一緒に活動してみたい! どんな活動をしているのか詳しく知りたい! という方は、ボラセンのInstagramやホームページをチェックしてみてくださいね! ■Instagram ■HP

保護者の方にもおすすめ
2617
2023.7.28
本学では学生の「やりたい」「学びたい」という気持ちを尊重し、学生が求める授業を数多く用意しています。今回はその中でも、全学共通科目(学科や学年を問わず、履修可能な授業)の『教養演習』に川崎重工業株式会社の永原様を外部講師としてお招きし、実践的なマーケティングの基礎を学ぶ講義を実施しました。 きっかけは地元神戸の商店街活性化事業『ミチニワまちびらき』イベント! この日の講義が実現したきっかけは、神戸三宮駅と元町駅の中間に位置する三宮本通商店街とセンターサウス通り一帯「ミチニワ」の活性化事業に本学が参加していることです。その事業の一環として、2023年3月に『ミチニワまちびらきイベント』が行われ、そこで神戸女子大学の吉川助教(心理学部心理学科)と永原様が出会ったことで具体的なお話が始まっていきました。 川崎重工業株式会社 永原様 「弊社(川崎重工業株式会社)は、同じ場所に偶然居合わせた人が、ネット上でコミュニケーションを取れるアプリ『Real D You(リアデュー)™』の開発を行っています。3月の『ミチニワまちびらきイベント』では、このアプリの実証実験を兼ねたイベントを実施させていただきました。その時に出会った吉川先生から今回の講義のお話をいただき、地域活性化を目的としたアプリの開発と運用の経験がお役に立つのならと思い、引き受ける決意をしたんです。自身の経験を伝え、実際の課題についても考えてもらうことで、学生の皆さんには活きた知識を得ていただければと思います。また大人だけでは生み出せない、学生ならではの純粋で自由な意見を聞けることにも期待しています。」 永原様は講師として学生に教えるだけでなく、講義を通して自分自身にも何か得ることがあるのではないか、と神戸女子大学の学生にも期待されていました。 ただの座学で終わらせない!実際の課題と手法を用いて知識定着を狙う この日の講義ではマーケティングの基礎として、まずは売り手目線の4つの基本戦略「4P分析」、買い手目線の4つの視点「4C分析」の説明がありました。内容の導入部分を少しだけご紹介します。 4Pとは…Product(製品)Price(価格)Place(流通)Promotion(販売促進)「企業側、売る側」の視点でマーケティングを考えること 4Cとは…Customer Value(顧客価値)Cost(顧客のコスト)Convenience(顧客にとっての利便性)Communication(顧客とのコミュニケーション)「顧客側、買う側」の視点でマーケティングを考えること さらに、レビットのドリルの穴理論を用いて、顧客がお店に本当に欲しいものが何なのか、顧客視点で考えることの重要性をわかりやすく解説してくださいました。 マーケティングの基礎を学生が理解したところで、本学の授業の魅力でもあるアクティブラーニング!実践的なテーマを課したグループワークの時間が設けられました。 学生の活発なディスカッションからプロも驚くような意見が生まれます。 今回のグループワークのテーマは… ネット上でコミュニケーションを取れるアプリ『Real D You(リアデュー)™』を利用してもらいたいペルソナ(ターゲットとする人物像)を自分達で考えて設定。そのペルソナの行動パターンを予想・分析。分析の結果、どのようなシチュエーションでどのような工夫をすることで成果があがるのか発表。 実際に利用されているマーケティング手法を用いているため、そのまますぐに実践できそうなアイデアや、少しのブラッシュアップで大きな成果が見込めそうな意見が数多く発表されました。学生のまっすぐな意見に永原様が耳を傾け、優しくアドバイスをくださる姿や、意外性のある女子大生ならではの意見にはお褒めの言葉をくださったシーンが印象的でした。 学生の知的好奇心を刺激する学びの秘訣は“現場目線” この講義ではグループワークの時間が設けられていることもあり、学生が主体的に意見交換を行うなど前向きに取り組む姿が印象的で、講義終了後に充実した表情で教室から出てきた学生から感想を聞くことができました。 「レビットのドリルの穴理論を聞き、顧客視点の考え方がなぜ重要なのか本当の意味で理解できました。グループワークを通して学んだ、顧客視点からのマーケティング手法はこれからも忘れないと思います。」 受講していた心理学科2年生の学生 「私は実践的な講義が多いことに魅力を感じ、神戸女子大学に入学したいと思いました。実際に入学してからも外部講師を招いた講義やフィールドワークも豊富でたくさんの経験をすることが出来ています。これからもさまざまな現場で活躍している方のお話を聞いたり、実践的なフィールドワーク、今日のようなグループワークをして、知識と技術を効率的にブラッシュアップしていきたいです。」 今回お話を聞かせてくれた学生が所属している心理学科では、1年次で心理学の基礎を学んだ後、2年次からは自分の興味に応じて、『臨床心理』『経営・消費者心理』『メディア心理』の3つの履修モデルを選択し、将来のやりたいことに直結する学びが得られます。 講義は終わりましたが、神戸女子大学と『ミチニワ』の商店街活性化事業はこれからも続きます!シンジョマグでも引き続き取材していきますので、今後の展開をお楽しみに!
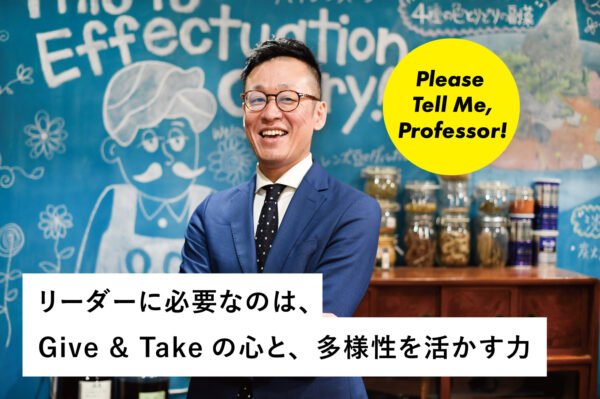
保護者の方にもおすすめ
1429
2023.5.10
リーダーには、さまざまな役割がもとめられます。育成、チームの運営・管理、課題解決のための目標設定……多岐にわたる問題を、さまざまな人々を指揮して解決に導く力が必要となります。 また、上層部と現場の板挟みになってしまい、大きな負担を抱えている方も多く居るかと思います。そんな問題を考える際に重要となる視点を、セブン-イレブン・ジャパンで長年多くの店舗を改善に導き、現在はまちづくりや経営コンサルティングを行う企業を経営する、心理学部 心理学科の吉川祐介先生に聞きました。 ⼼理学部は、さまざまな専⾨分野のスペシャリストが集結しています。そのなかでも、吉川先生の専⾨はマーケティングなどを扱う商学であり、⼼理学の学びを実社会でどう活かすか、そして、経営の視点を加味することに関わっています。 チームメンバーの努力を促す、関わり方と育成のポイント Give & Takeが基本ルール マネジメントの基本的な考え方として、「誘因と貢献」があります。一般的な言葉で表現すると、「Give & Take」です。 基本的に、組織(企業など)が個人に価値を提供できていれば、個人は組織に対してきちんと貢献してくれます。しかし、提供する価値が、個人の貢献と同等かそれ以上のものとなっている必要があります。チームメンバーが、なかなか成果をあげてくれないのであれば、まずは自分がメンバーに何を提供できているのかを考えなければなりません。人は「自分は損をしている」と考えがちで、利益よりも損失を過大評価してしまう傾向があります。「これだけやってあげているのに、なにも返してくれない」と思ってしまった時は、一度冷静に立ち止まり、「メンバーが求めているものはなにか」「それを提供できているのか」に気を配ることを強く勧めます。 また、リーダーは自分を含めたチームメンバーがもつ価値を客観的に見つめる必要もあります。たとえば、企業がSNSを使った広報を考える場合、上司世代よりも新人世代の方が高いITリテラシーを持っていることが多々あります。そのような状況では、新人世代の知識や経験の方が価値をもつ可能性は十分にあります。自分自身に「経験や知識」というアドバンテージが何事にもあると思っていると、与えるべき「Give」を見過ごしてしまいます。 人は自由を奪われるとやる気をなくす生きもの 心理学の用語に、自由を制限された際に「やりたくない」「ここから出たい」など、自由を取り戻そうとする性質を意味する「心理的リアクタンス」という言葉があります。 「部下の意見や判断を尊重しなければならない」という言葉をよく耳にするのは、「そうしなければ部下の心理的リアクタンスにより組織の破綻につながる力が作用する」という背景があるからです。心理的リアクタンスを回避するには、選択肢を与えたり、判断や意見を聞いたりするなどして、裁量を与え、自律的に自由意志を表現できるプロセスを用意することが重要です。 チームのリーダーには「自分がやった方が効率よく進められる」というバイアスがかかりがちです。生真面目な人ほどついつい何もかも抱え込むことが多いですが、大抵の場合任せるべきものは権限を渡した方が効率的に進みますし、心理的リアクタンスの回避につながります。 バイアスを自覚した上で、メンバーの意見・判断にしっかり耳を傾けて、選択肢を増やすことが、チームや組織の発展には必要不可欠です。 褒めるだけでなく、目標に合わせた適切なステップアップを 成果に対して評価をすることは、リーダーがチームへと与えられる価値のひとつですが、「褒める」という行為も単純に行ってしまえば、成長を止めてしまうことに繋がります。もちろん、適切な評価をポジティブに与えることは良いのですが、人は褒められると気持ちがどうしても緩むので、同時に次のステップも用意しておかないと、力が抜け切ったままになってしまいます。状況・目標にあわせたステップを適切に用意することが、成長に繋がっていきます。 「なにを選ぶのか」ではなく「なぜ選ぶのか」が重要 チームづくりには、「めざすべきもの」を明確にすることが基本です。たとえば、居酒屋で「ジョッキになみなみ注がれたビールを提供するのか」、「コスト管理をして適量を出すのか」どちらが正しいか考えてみましょう。 なみなみ注がれたビールに満足したお客さんは、リピーターになることが期待できます。一方で適切なコスト管理で収益が上がると、従業員が余裕をもって働ける環境がつくれます。そして従業員満足度が高い店は、お客さんの満足度も高い傾向にあります。お店の経営としてはどちらも正解です。言い換えれば、答えがないということです。 そして、世の中の大半のことには、「これをやれば大丈夫」だという答えはありません。漠然とした考えで答えのない問いから選択肢を選ぶと、行動の指標がないため、中途半端な結果になってしまいがちです。 そのため、「なぜそれを選ぶのか」が重要となります。答えのない問いを多角的な視点から考察し、「自分たちがめざすべきものは何か」というビジョンをはっきりさせることで、選択に説得力が生まれ、中途半端に終わらない明確な行動につながっていきます。 新たな価値を生み出す多様性の重要性と、心理的安全性 「正解が分かっていること」の解決は誰でも簡単にできるため、高い価値を生み出すことはできず、激しい価格競争にも巻き込まれ、チームは疲弊しつづけてしまいます。現代では、あらゆる物事が変化し続ける状況の中から「新たな価値を生み出すこと」が求められるため、さまざまな視点から意見を交換しなければ、価値を創出するアイデアを見つけ出せません。 だからこそ、ビジネスをふくむあらゆるシーンで、多様性を重視することが叫ばれているのです。多様性を保ち、幅広い意見の交換を行うには、「心理的安全性」が必要となります。「心理的安全性」とは、「チーム内で自由に率直な意見を発言でき、関係性が壊れず、罰せられる心配のない状態」のことです。 「課題解決のために意見を言ったのに、考え方が違うだけで全否定された」などということがあれば、メンバーは自分の意見やノウハウを提供しなくなり、新たなアイデアが生まれづらくなるため、チームに大きな損失を招いてしまいます。非常に難しくはありますが、チームリーダーはそのようなすれ違いを起こさぬように、常に注意を払いながらメンバーの意見に触れる必要があります。 多様性の落とし穴 多様性を保つことは重要ですが、意見の多様性が増せば増すほど、リスクの低い中庸的な答えに議論が集約されてしまうことが多々あります。また、それとは反対に、リスキーな志向が強い人が多ければ、極端な方向へ振り切ってしまうこともあります。 そこに、多様性を重視したチームや議論の落とし穴があります。ただ単に議論の流れがそうなったからと言って、それが本当に自分たちのめざすべきものかどうかは、立ち止まって再度考える必要があります。そもそもなぜ多様な意見を集めるのか、そしてそれで何をめざしたいのか。そのようなビジョンをチームメンバーに共有しておくことで、多様性を重視した議論やチームづくりは、より効果的なものに近づきます。 「板挟み」を乗り越えるために 中間管理職などで陥りがちな、上層部と現場チームの「板挟み」を解消するには、個人的な見解にはなりますが、「現場との良好な関係性」を長期的に築き続けることにあると思います。上層部の考えを直接変えることは、個人の力では不可能に近いです。しかし、自身が指揮するチームの管理方法や、関係性を変えることは可能です。 長期的な目標を持ってチームを管理すると、「今月契約を100件取る」といった短期的な成果は上げづらく、直属の上司にはなかなか評価されません。しかし、経営陣などさらに上位の人々は、長期的な視点で経営を行う立場のため、チームの底上げとなる取り組みはきちんと評価して、フックアップしてくれる可能性があります。 また、現場チームと「誘因と貢献」・「多様性の担保」・「新たな価値の創造」など、長期的な視点を持たねば解決できない難しい課題に取り組むのは、独立や転職など組織を離れる選択を可能とするマネジメント力を養うことに繋がります。長期的な視点で、根気強く現場と真摯に向き合いつづけることこそが、解決の糸口になるのだと思います。 答えのない問いを考える学び 「新たな価値を生み出す力」を育む、神戸女子大学 神戸女子大学では、今回お伝えしたような「価値を生み出す力」を重視した学びが展開されています。たとえば心理学部 心理学科で私が担当する授業では、過去に神戸で名物として親しまれたカレーの復刻版の広報プランや、こども食堂における悩み事の解決策の考案など、自分で問いを見つけ出し、自分なりの答えや価値を導きだす力を育む学びを展開しています。 学生たちがチームを組んで、自分たちが培ってきた心理学の知識を、現実の中でどのように活かし、ビジネス的な課題をふくめて解決するかを、私の経営学的な知見を伝えながら、考えてもらっています。今回お伝えした「多様性」「心理的安全性」といった問題に直面しながらも、答えのない問いに日々真剣に取り組む学生たちの姿を見て、「先行きの見えない社会だけれども、この若者たちがいるからきっと大丈夫だ」と勇気を与えてもらっています。 プロフィール心理学部 心理学科吉川 祐介先生 大阪市立大学 経済学部 経済学科卒業後、株式会社セブン-イレブン・ジャパンに就職。店長を経て、各店舗の経営者を支援する職務に就き、多くの経営不振に苦しむ店舗の経営改善を手がけた。その後、神戸大学大学院 経営学研究科で経営理論に磨きをかけ、大学院修了後は、まちづくりや経営コンサルティングを行う個人事業を開業。現在は、株式会社けいえいまちの代表取締役として活躍。

オープンキャンパス特別企画
773
2023.5.8
プロのデザイナーと協働で創り、回を追うごとに進化するオープンキャンパス。在学生との会話もぜひお楽しみください!

神女サポート
2619
2023.1.30
2022年5月、神戸女子大学ポートアイランドキャンパスに『神女ポーアイボランティアセンター』が設立されました。実はこのボランティアセンターは学生が主体となって設立した団体です!今回はそこで活動する学生にインタビューを行いました。 学生と地域を結ぶボランティアセンターの代表の学生にインタビュー! 代表を務める社会福祉学科2回生のKさんにお話を伺いました。 ―ボランティアセンターを設立したきっかけを教えてください。 1回生の3月まではコロナの影響もあり、充実した学生生活が送れているとは感じられず、『何か変えたい!』と思っていました。そこで思い切って地元のボランティアセンターを訪ねましたが、コロナ禍でボランティア募集があまりなかったため、規模が大きい大阪ボランティア協会が主催する【初めてのボランティア説明会】を紹介して頂けることになり、参加しました。そこで出会ったボランティアコーディネーターの方に、大阪公立大学のボランティアセンターと大阪ボランティア協会が主催する「ソーシャルイノベータープログラム」という若者の事業立ち上げプログラムをご紹介頂き、そこで主体的に活動する他大学の団体から多くの刺激を受けました。そんな時、大学のボランティアセンターの多くは学生主体で立ち上げる事例が多いと知り、私と同じように『何か変えたい』と思ったシンジョ生が立ち寄れるボランティアセンターを作ることが出来るならと思い、自分で立ち上げよう!と決意しました。 ボランティアセンター 代表のKさん 社会福祉学科2回生 ―立ち上げ時はどのような苦労がありましたか? すでに団体立ち上げのプロセスを学んでいたので、とても苦労したという感覚はそれほどありませんでした。ただ、ホームページの作成や活動時の交通費など、資金面で大きな壁があることに気づかされました。当然私個人で工面することは難しく、現在の顧問の先生に相談させていただきました。そこで『神女support』という助成金についてお聞きし、応募したんです。すぐに資金調達ができたおかげで、設立から約半年ですが様々な活動ができたと思います。 ボランティア活動時のTシャツも助成金を使用してすぐに作成し、課外活動時に着用 ―普段はどのような活動をしていますか? 現在スタッフは8名で、今年は私達の存在をたくさんの団体の方々に知って頂くためにも他のボランティア団体がまとめる既存企画に多く参加しました。ボランティアセンターとしては学生が充実した生活を送れるよう、広報部とコーディネート部、企画部に分かれて活動しています。長期休み前などには告知を行うので、ボランティアに限らず、現状を変えたいという方はぜひ相談に来てください。全力でサポートさせていただきます! ―今後の目標について教えてください! これからは私たちが発起人となって、周りを巻き込めるような大きなイベントを企画したいと思います! センターのスタッフたちの打ち合わせの様子 ボランティアセンターの命運を握る広報担当の仕事とは? 広報担当として活躍中の社会福祉学科2回生Mさん。スタッフになったきっかけや、広報担当としてのお仕事についてお聞きしました。 ―スタッフになったきっかけは? ボランティアセンターのインスタでKさんの活動を目にし、挑戦する姿に刺激を受けたことです。当時、私も学外で何か経験を積みたいと考え、7万人ほどのフォロワーを抱えるインスタグラムアカウントの運用を担当していたので、その経験を活かしたいと思いスタッフとして参加しました。 広報担当 Mさん 社会福祉学科2回生 ―広報担当就任後はどのようなことに着手しましたか? 投稿の系統を揃えることから始めました。投稿内容が見づらいと内容が伝わりにくいので、見やすさを意識しています。 ポーアイボランティアセンターのInstagramはコチラ ―苦労した点を教えてください。 ボランティアセンターのアカウントでは、活動により興味を持っていただけるよう、現場の空気感を動画や画像で伝える必要がありました。単に情報を伝えるだけではいけないという点に苦労したんです。これは他のボランティア団体の投稿を参考にすることで日々改善しています。 ―インスタグラム以外の広報は? ホームページとLINE、あとは1年間の活動内容をまとめた雑誌の制作もしています。楽しみにしていてください! ―ボランティアセンターの活動を通して得たことは? 学生主体で活動するため、誰かが先頭に立つべき場面がよくあります。そのような時に『自分が』という責任感が芽生え、定期的な会議なども率先して取り仕切るようにしています。これからの目標は『シンジョといえばボランティアセンター』といわれるようなアカウントを目指して、広報活動を続けていきたいと思います。 設立間もないボランティアセンターでは1回生も主力として活躍中! 設立から約半年で多くの実績を残してきたボランティアセンター。その一翼を担う1回生、HさんとSさんにもインタビュー! ―ボランティアセンターのスタッフになったきっかけと、印象に残っている活動を教えてください。 もともとボランティアに興味はあったんですが、参加の機会にはなかなか恵まれませんでした。そんな時、大学の職員の方から代表のKさんを紹介していただき、その場でスタッフになることを決意しました。 Hさん 心理学科一回生 印象的な活動は、10月に神戸で2日間にわたって開催された『防災推進国民大会2022』です。1日目にワークショップを行い、私は2日目にその成果と感想を発表したのですが、お子様から大人の方まで真剣に話を聞いてくださる姿が印象的でした。私も含め、そのイベントで防災意識が高まったという方も多いと思いますし、イベント参加をきっかけに自分の中の新しい扉を開くことができるのは、ボランティアセンタースタッフに参加して良かったと思えます! https://youtu.be/6lUYEPm8pF4 Hさんをはじめ、ボランティアセンターの学生が参加した防災国体2022 私は大学で何をするか迷っている時、代表のKさんが講義前にボランティアセンターの紹介に来られたことがきっかけです。その時のお話から、私もスタッフとして活動し、学生生活を充実させたいと思い参加しました。 Sさん 社会福祉学科1回生 私が印象に残っている活動は『須磨海岸クリーンボランティア』です。この活動ではごみを集めるだけでなく、それを何かに利用できないかと考え、拾い集めたプラごみを材料にしたレジンアクセサリーのワークショップを学園祭で行うことにしたんです。 活動の様子はコチラ 私は趣味でレジンのストラップなどを作っていたので、力になれるのではないかと思い、積極的に参加しました。事前に何度か試し、説明書も自作して迎えた当日は大きな失敗もなく進めることができました。後日、作ったアクセサリーをスマホに付けている方を見かけたときはうれしかったです。 須磨海岸のイベントでは、やり遂げたという達成感が得られただけでなく、自分が何かの役に立つことができたという自信もつきましたし、活動を通して環境についての理解も深まりました。来年度も多くのイベントに積極的に参加していきたいです! プラごみをかわいいレジンアクセサリーにリメイク 最後に代表のKさんから高校生とシンジョ生に一言お願いします! 今在籍している学生スタッフも『何か変わりたい』という想いから参加しています。漠然と『何か変わりたい』という想いを抱いている方は、一度私たちを訪ねてくれればうれしいです!また、4月からは神戸市社会福祉協議会さんとも協力し、活動内容ももっと充実していきます! ご質問やボランティアセンターに興味をお持ちのシンジョ生は、お気軽にInstagramのDMへ!またはホームページからボランティア情報サービスの登録をお願いします!