
特集
605
2025.1.31
文学部史学科の考古学ゼミが神戸市西区の金棒池古墳を発掘調査すると聞き、取材を行いました!6世紀につくられた古墳の調査の様子をレポートします。
金棒池古墳は、神戸市西区にある金棒池の中にあります。周辺で採集された土器から6世紀頃につくられたと考えられています。6世紀は古墳時代の終わりが見え始めた変革の時期。そんな中で築かれた金棒池古墳は、まさに「神戸市最後の前方後円墳」とも言える存在かもしれません。
この古墳の全容を明らかにすべく調査に乗り出したのが、文学部史学科の齋藤瑞穂准教授!神戸市の「大学発アーバンイノベーション神戸」の助成金を受け、本格的な調査に着手したのです。


調査の現場となる金棒池古墳はため池の中にありますが、冬の時期は水位が下がるため、その時期を狙って調査を実施することになったそう。土を掘り返し、どこまで古墳があったのか、土や砂の層をよく調べていきます。


冷たい北風が吹きつけ、時折粉雪が舞うような現場でしたが、齋藤先生をはじめ誰も手を止めることなく、懸命に作業を続ける姿が印象的でした。
文字で書かれた記述が少ない時代の歴史は考古学の方法でアプローチしていくのが最も有効です。齋藤先生の研究領域はまさにその最前線。神戸女子大学は発掘調査を行っている全国でも珍しい女子大学です。
少しずつ掘っていくと、色が異なる土や砂の層が見えてきました!じっくり観察して、それらがいつ堆積したものかを検討していきます。

参加した史学科3回生のKさんに、『やり直しの効かない作業に不安が大きいのでは?』と伺ったところ、「大学の講義や論文で学んできたことを、調査で活かすことができてとても楽しいです!」と満面の笑みで答えてくれました。

経験豊富な齋藤先生の背中を見ながら、実践的な学びが得られた貴重な機会。「将来は埋蔵文化財にかかわるような特に発掘に関連した仕事に就きたいです」と夢を語ってくれました。
「金棒池古墳」の発掘調査は、2025年度も継続予定。先生や学生たちの作業により、これからも一歩ずつ、歴史の解明が進んでいくことでしょう。そしてこの調査が、博物館学芸員をはじめとする歴史のプロを数多く生み出すきっかけになっていくことを、強く期待したいと思います!
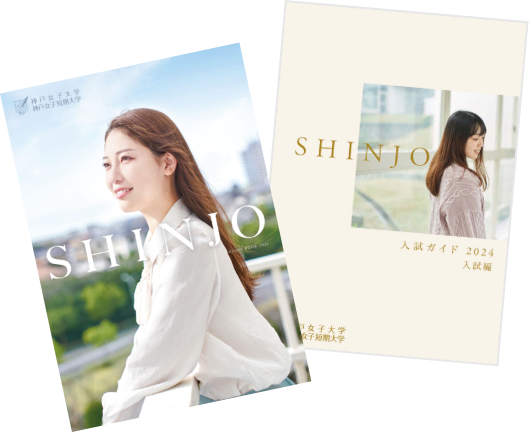
学校のこと、学び、先輩、就職。
シンジョの
リアルと魅力が詰まった冊子や入試ガイド
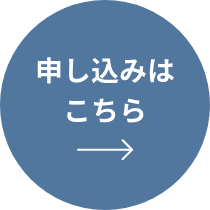
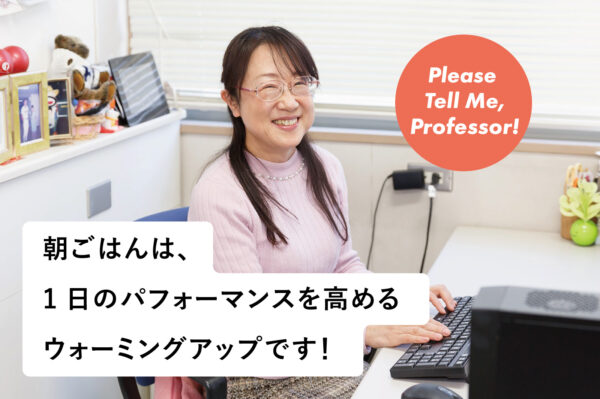
保護者の方にもおすすめ
7554
2023.5.10
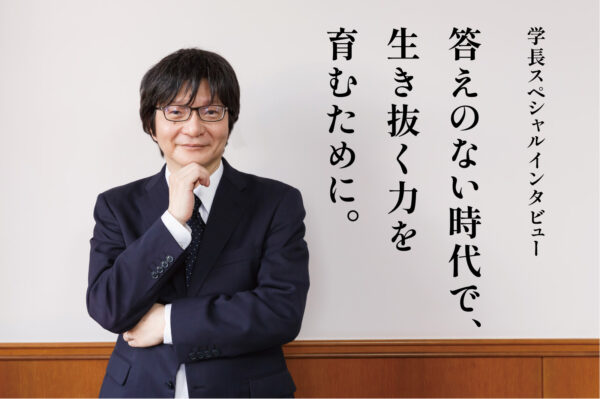
保護者の方にもおすすめ
3912
2023.4.24

特集
7282
2023.1.6

特集
5982
2023.1.6

キャンパス
2555
2024.2.22

特集
3370
2023.1.6