保護者の方にもおすすめ
2025.07.25
Read the article
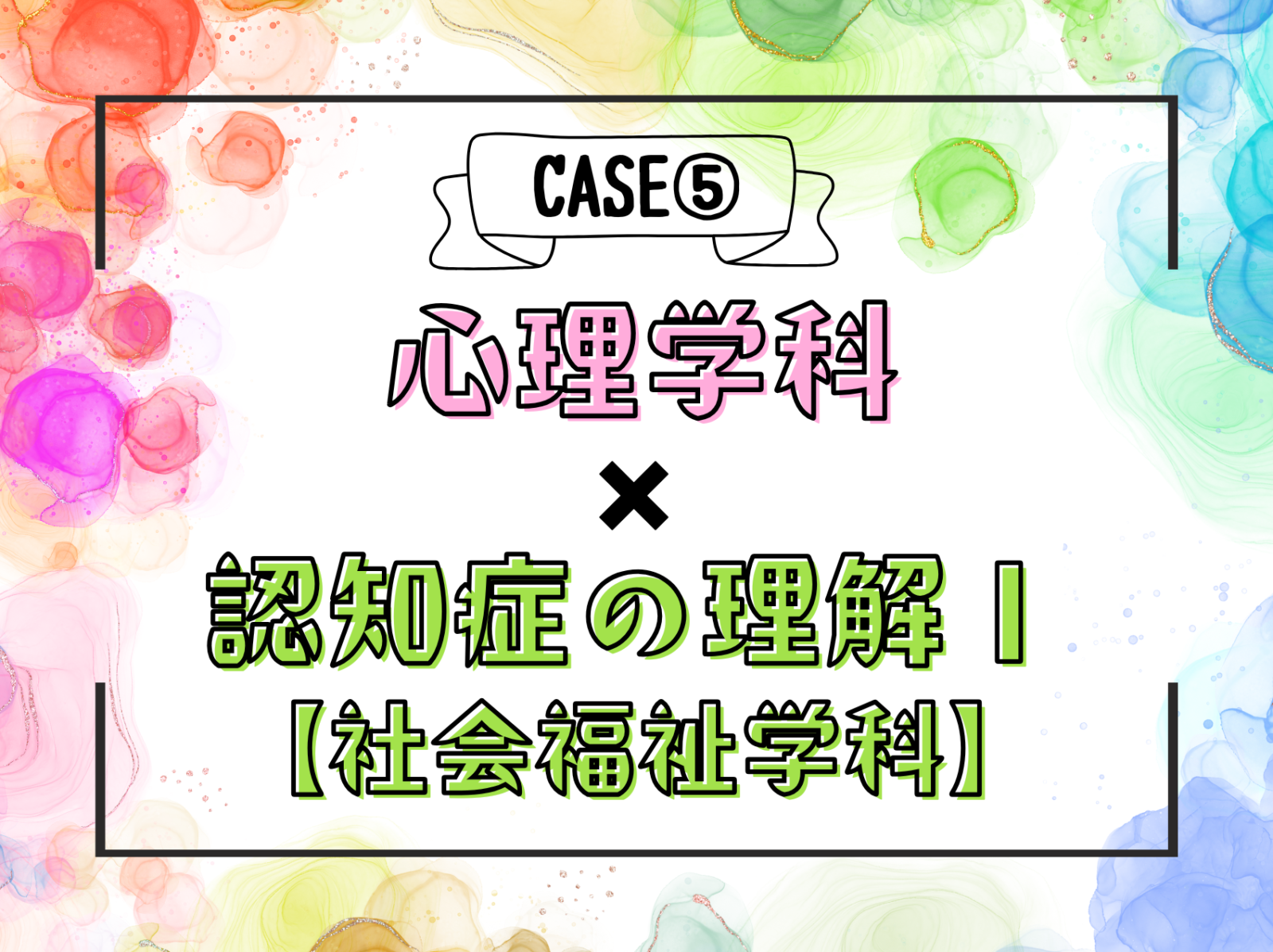
保護者の方にもおすすめ
2025.07.25
Read the article
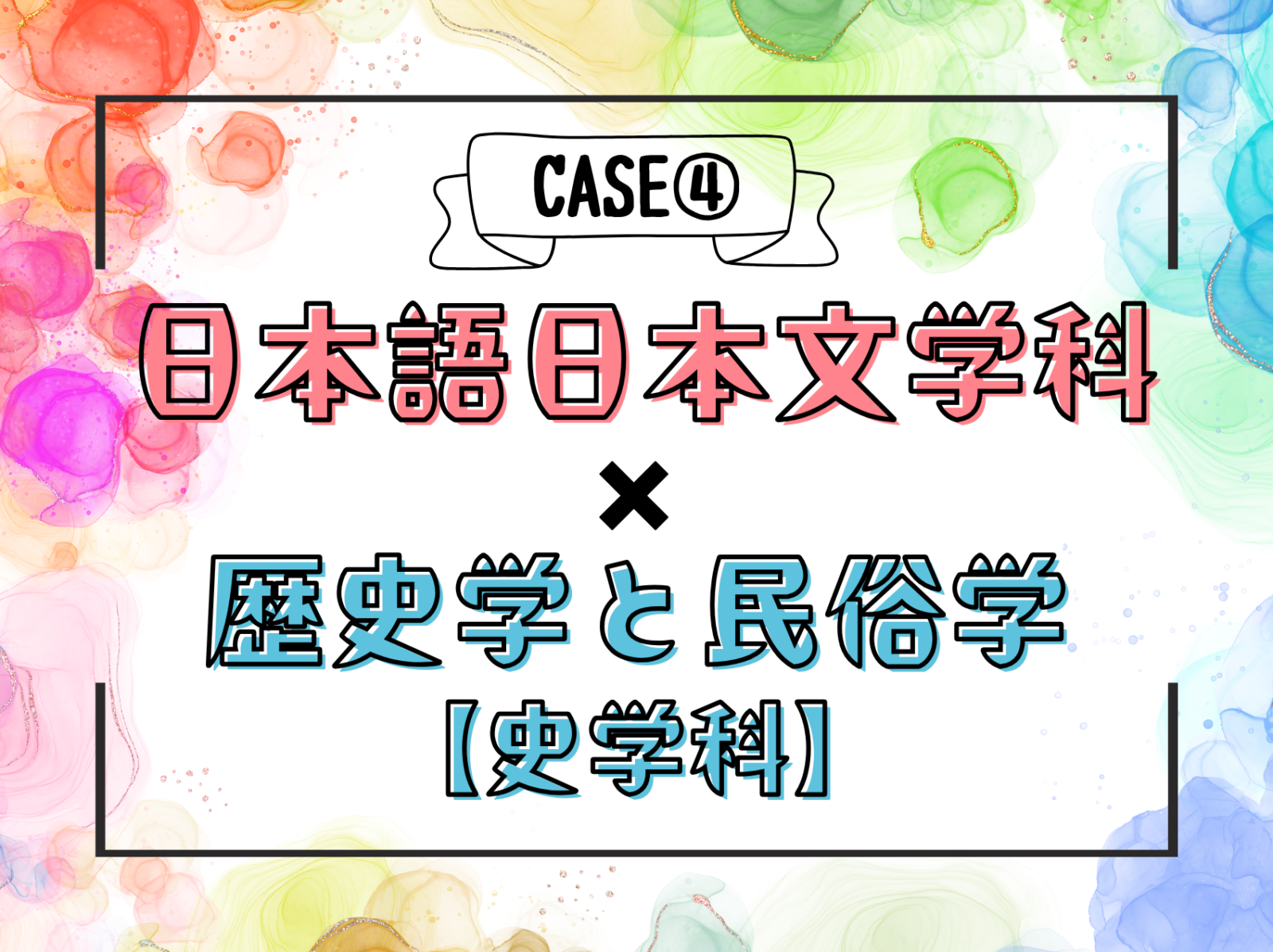
特集
2025.06.30
Read the article

特集
2025.04.14
Read the article

キャンパス
2025.04.04
Read the article

Recommend
オススメ記事

神女サポート
1,946
2024.9.20
「ポートアイランドに新たな交流の場を!」をモットーに活動を行う神戸女子大学の学生団体「ぐるりと。」現在は地元地域にお住まいの方々を対象に子ども食堂を開催しています。 そんな「ぐるりと。」は2024年に社会福祉学科の学生を中心に設立されたばかり。今回は初めて実施した子ども食堂の様子と併せて、団体の代表を務める学生たちにどんな思いでこの活動を始めたのかインタビューしました! 子ども食堂とは… 子どもたちやその家族に対して無料または低価格で食事を提供することや、勉強や宿題のサポートなどを行う地域密着型の支援活動です。主に地域の支援団体やボランティアが運営していることが多く、地域の子どもたちが安心して過ごせる居場所として、また地域の人々の交流の場としても近年広がりをみせています。 「ぐるりと。」結成のきっかけは授業後の雑談⁉ 結成のきっかけは、発起人であるMさんが一回生の時にインターンシップで参加した子ども食堂について、ある授業の中で発表したことでした。その授業が終わったあとにその発表を聞いていた他のメンバーが話しかけたのです。 メンバーはそれぞれが別の友人グループに所属しているそうですが、その日をきっかけに日頃学んでいる社会福祉について語り合う仲になっていき、「自分たちで地域貢献がしたい!」という強い思いから結成されました。 そんな「ぐるりと。」は、『やりたいこと』の元に個性豊かな学生が集まり、ポートアイランドの地域の方々が『ぐるりと』一周、みんなが手を繋いで、誰ひとり取り残されることがないような支援活動を目指しています。 団体結成後まもなく、メンバーは地域貢献のために何ができるかを考え、Mさんの経験をヒントに地域の子どもに無料で食事を提供する「子ども食堂」を開くことに。こうして地域貢献への第一歩を踏み出したのです。 各所への申請、調整から告知まで。自分たちで行った準備期間 やることが決まれば、あとは前に突き進むのみ!しかし、子ども食堂を実施するまでの道のりは想像以上に大変だったと学生たちは話します。 Mさんは「企画段階からたくさんの方にお世話になりました。やりたいことを実現させるためには、キャンパス内の場所の調整から提供するお弁当の準備、それを提供するための許可申請など…やらなければならないことが想像以上に多くて。 ひとつのイベントを実現させるためにこれだけの準備が必要だということを痛感したと同時に、地域の夏祭りや高校の文化祭などを楽しめていたのは、その時に自分の周りにいた大人の方々の努力があったんだなぁと思いました。 そして、これからは私たちが楽しんでもらう側になっていくんだ!と責任感も強くなりました。」 積極性を活かして関係各所との調整、相談を主に担当するMさん 各所への許可申請書類の作成などを中心になって担当したTさんは「神女support(助成金)の申請書類をはじめ、飲食物を提供するためなど様々な申請関係を担当しました。長い時間をかけて準備してきたことが今日、本当に形になったんだという達成感があります。 でも、これに満足せず、地域のみなさんが集まる場所を創る側として引き続き活動していきたいと思います。」と意欲高く語ってくれました。※「ぐるりと。」の運営には『神女support(学生課外活動助成金制度)』が使われています。 神女support(学生課外活動助成金制度)学生による自主的な課外活動(地域貢献やボランティア等、地域の課題解決や活性化を推進する取り組み)を支援する独自の助成金制度。活動に必要な資金の助成を受けることができます。詳しくはコチラ! 書類作成やイベント当日の運営準備などを主に担当したTさん 各種申請書類が完成してからも、新たな困難が彼女たちの前に立ちはだかります。それは参加者への広報、子ども食堂の告知です。いくらイベントを実施しても参加者がいなければ成り立ちません。たくさんの人に「ぐるりと。」の存在と、自分たちが開く子ども食堂を知ってもらうための広報活動が必要です。 当初は自分たちの手元にあるスマホでSNSを使って発信しようと考えていましたが、それ以外の広報活動にも着手していきました。まずは、保育園や学習支援教室のような子育て世代の方々が利用している施設をリストアップして訪問し、チラシの設置をお願いして回りました。 他にも、地域ごとのイベントが調べられる情報サイトに掲載するなど、『知って欲しい人に情報を届ける』という意識をもって広報に取り組み、子ども食堂の初日を迎えました。 いよいよ当日!たくさんの子どもの笑顔が溢れた一日 子ども食堂当日。開始の1時間前に集まった「ぐるりと。」の学生たち。これから始まる子ども食堂を円滑に進めるための打ち合わせを行います。地域の人々に安心・安全な場所を提供することはもちろんですが、「参加してよかった!」と思ってもらうためにも、学生たちの打ち合わせや確認作業に余念はありません! また、子どもだけで参加する場合はキャンパスの最寄り駅まで「ぐるりと。」メンバーがお迎えにいく送迎サービスも実施しています!ご家族も安心ですね。 子ども食堂「ぐるりと。」へようこそ! 実際に提供したハンバーグ弁当。おいしそう! 開始後まもなく、子ども食堂の会場は来場者のみなさまでいっぱい!友達同士で、そしてご家族みんなで美味しいお弁当を楽しく食べ、笑顔と笑い声で溢れる空間に。 子どもたちが食後にも楽しい時間を過ごせるように、レクリエーションを準備していた学生たち。多目的ルームを覗いてみると「ハンカチ落とし」で大盛り上がり!ご家族の方々はこの様子を席で見守りながら保護者同士の交流タイム。 この躍動感溢れるハンカチ落としは元気いっぱいの子どもならでは! そして、別の部屋を覗いてみると小学校低学年などを中心に「手遊び歌」のレクリエーションが行われていました。小さな子どもたちにも楽しんでもらえるように活動する学生たちの姿から、「ぐるりと。」らしい『誰ひとり取り残されない活動』の理念を感じることができました。 はじめはゆっくりですが、どんどんテンポアップしていく手遊び歌にみんなが夢中に。 「ぐるりと。」の子ども食堂は営業時間内であれば何時に来ても大丈夫!たくさんの方が来場し、食事やレクリエーションを楽しんで帰路につきます。初めての営業でしたが100名以上の地元地域の方々にご参加いただくことができました。そして、綿密な打ち合わせの成果もありトラブルなく無事に一日を終えることができました。 「ぐるりと。」の活動は始まったばかり。今後の展開にも期待大! 今回、美味しいご飯と楽しいレクリエーションを行う「子ども食堂」を開催し、モットーである「ポートアイランドに新たな交流の場を!」を見事に実現させることができた学生は充実感を感じていました。 ご参加いただいた方々にご挨拶するMさん 「ぐるりと。」の発起人であるMさんは、「1組でも来てくれたらいいな…という気持ちで始めた子ども食堂でしたが、思った以上の反響があって驚いています。たくさんのニーズがあることが分かったので、周りの期待に答えたい気持ちでいっぱいです!」と語ってくれました。 今後も子ども食堂を定期的に実施していく予定で、実施回を重ねるごとに、宿題や勉強をサポートする「学習支援」や、子ども食堂の食事支援が必要な人のご自宅まで食事を届ける「配食サービス」の導入も検討している「ぐるりと。」の今後の活動に期待が膨らみます! 「ぐるりと。」のInstagramはこちらから。

神女サポート
3,496
2024.3.7
神戸女子大学の学生有志団体「潮見会」が、神戸市立須磨離宮公園の活性化を目的として同公園内の建物をカフェとして本格リノベーション!本オープンは2024年5月以降を予定しています。今回はプレオープンイベントの日に現地に伺い、いったいどんな建物ができたのか、その出来栄えとこれまでの経緯などを取材しました。 リノベーション…間取りから内装・配管などをゼロから考え直し、これから使用する用途に合わせてつくり替えること 企画立案から今後の運営まで、主役は常に学生たち! このリノベーションプロジェクトは2022年11月に始動し、学生団体『潮見会』のメンバーが中心となっています。リノベーションが行われる場所は、須磨離宮公園にある「潮見台休憩所」。プロジェクトが始動した直後の現地視察時には、10年以上前に売店として活用されていたテナントとベンチがありました。ここをどんな建物に生まれ変わらせるのか、そしてその建物で何をするのかは学生たちに一任されています。 リノベーション前の現地視察の様子 活動当初、自分たちの好きなモノを活かしつつ、SDGsを意識してリユース・リサイクルを促進する古着屋をオープンする構想を持っていたこともありましたが、プレオープンでお披露目されたのは『Flower Cafe Bloom』というカフェ。 ここが こうなりました! この経緯についてFさんは「私たちが考えたものが公園利用者のニーズに応えられているのかを確かめるために、来園者にアンケート調査を行いました。その結果、利用者は気軽に立ち寄ることができるお店を求めていることがわかったんです。その結果を参考にして構想を練り直し、『Flower Cafe Bloom』をオープンすることなりました。」と語ります。 カフェをオープンすることが決まると、次はコンセプト設計。一言でカフェといっても、オシャレ・隠れ家的・アメリカン・古民家・大人っぽい、など色々なコンセプトが思い浮かびますが、『リラックスできて、須磨離宮公園になじむカフェ』をコンセプトに、お店のレイアウトやインテリア、ロゴを考えたそうです。 店舗前の吊り下げ看板にはロゴが。 外観は白の壁面にあたたかみを感じる木材が映える上品な装い。しかし、これも当初は別案があったとFさんは話します。「はじめは若者に人気のネオンライトを活かした韓国風カフェも候補に挙がっていました。しかし、アンケートをもとに定めたコンセプトを軸に何度も軌道修正をして今の形になりました。」 「インテリアについても、メンバー内でいくつも候補が出たのですが、コンセプトを念頭に話し合いを進めることでスムーズにまとめることができました。椅子の高さは、家政学科で住環境を学んだメンバーの意見を参考に、座りやすい適切な高さの物を採用するなど、細かいところにもこだわっています。」 客席に設置したこだわりの椅子 照明も色味、サイズなどこだわりがいっぱいです シンジョでしかできない経験が、学生の成長を後押し! 図面作成などにも携わった潮見会の学生たち。その貴重な経験について聞いてみました。 「レイアウトやコンセプトイメージを建設会社の担当者様にお伝えし、作成いただいた図面に対して微調整を繰り返すことでまとめていきました。希望を全て叶えようとすると費用は際限なく膨らみます。当初決めた予算を意識しながら、理想を叶えることにとても苦労しました」と語るFさんは、この問題を希望するレイアウトの一つひとつに優先順位をつけることで解決したそうです。 「どうしても外せないお店のシンボル、ドライフラワーを飾るショーケースや、店内に開放感を与える大きな窓は外せないものとしてお伝えしました。一方で、支払いや商品の提供をするカウンターと厨房の間の仕切りは、当初想定していた扉から暖簾に変更することで、費用を抑えることができました。図面を書いたり、頭で考えるだけではなく、それが実際に形になるなんてなかなかできない経験だと思うので、とてもやりがいを感じました。」 開放感溢れる大きな窓がある店内スペース 変更した暖簾はオシャレで使い勝手も良好! 当時、建物担当としてメンバーをまとめていた家政学科2回生のKさんは、「今までにやったことのない大きな経験だったので、次から次へと起こる問題に対して、皆の意見をまとめることに苦労しました。それでもテキパキと物事を進めていく先輩の姿に刺激を受けながら、楽しくやり遂げることができたのはこのプロジェクトに参加しないと味わえない経験でした。」と振り返ります。 プレオープンは大盛況! 学生に届くたくさんの反響と大きな期待 『Flower Cafe Bloom』という名前は、お客様一人ひとりを須磨離宮公園の代名詞といえる『花』に例え、花が満開に咲いている=「いつまでも人が集まるお店になるように」と願いを込めてつけられています。 bloom…「開花、全盛期、花盛り」などの意味。 名前に込めた願い通り、オープンと同時にお店にはたくさんのお客様が! 学生たちはお客様から「いつもベンチで休憩させてもらうけど、こんなお店があると活気があっていいね」「いつからオープンなの?本オープン後もまた来るからね」といった温かい言葉をかけてもらっていました。 この日ご来店いただいたお客様のほとんどは、公園の入り口などに貼り出していたチラシを見て来られたそう。このチラシの印刷や店舗で必要な機器の購入には『神女support(学生課外活動助成金制度)』が使われています。 集客効果抜群だったチラシ 右手前のショーケースは保温も冷蔵も出来る優れモノ 学生課外活動助成金制度(神女support)って?学生による自主的な課外活動(地域貢献やボランティア等、地域の課題解決や活性化を推進する取り組み)を支援する独自の助成金制度。活動に必要な資金の助成を受けることができます。詳しくはコチラ! 今回のプロジェクトに協力してくださっている神戸市立須磨離宮公園の職員の方にお話を伺うと、「公園の利用者は年配の方や小さなお子様を連れたご家族が多く、大学生が持つ明るさや活気に魅了されているのだと思います。これから須磨離宮公園の活性化を促す、新名所になってくれるのではないかと期待しています。」と語ってくださいました。 大成功を収めた「潮見台休憩所」のリノベーション。『Flower Cafe Bloom』の本オープンは5月以降を予定しており、オープン後はワークショップや子ども向けイベントなどの企画も構想中です! 在学生のみなさんへ『Flower Cafe Bloom』の運営に興味のある学生はこちらからお気軽に問い合わせを!『Flower Cafe Bloom』Instagram

特集
2,749
2023.12.14
さまざまな企業と産学連携の取り組みを行っている神戸女子大学。今回タッグを組むのは、「フジッコのおま~めさん」のフレーズでお馴染み、自然の恵みを大切にしながら商品開発を続けるフジッコ株式会社。(本社:神戸市) 同社の看板商品である「おまめさん きんとき」は、つややかできれいな見栄えが求められるため、生産工程で出る皮の破れた豆は製品に使用せず食品ロスが発生していました。 しかし、この豆は皮が破れているだけで品質には問題がなく、おいしさは同じです。何とかして価値あるものに生まれ変わらせることはできないか…。 そしてもう一点、若者の豆離れにも一石を投じることができれば!ということを考え、『Z世代がZ世代のために考えた ちょっと高くてもついつい食べたくなる豆アイスの商品企画』がスタートしました。ちなみに、この特別講義は「教養演習1」という講義。学部学科の垣根を越えて、さまざまな学生が受講しています。 今回は、学生がこれまでの講義を踏まえて企画したオリジナル豆アイスを、フジッコ株式会社の役員や各部署の部長職など錚々たる面々にプレゼンする中間発表の日を取材しました! 看板商品である おまめさん きんとき 役員、各部署長の皆様もお越しくださいました。 各講義は「講座」「活用例」「実践」の3ステップ力をつけながら商品企画を行う 産学連携で行われるこの商品企画プロジェクトは、全13回にわたります。本格的なマーケティングの知識と商品企画について、現場の第一線で活躍されているフジッコ株式会社の只野さんから直接ご指導いただき、学生ならではのアイデアで新しいアイスを企画。最終的なゴールである商品化を目指し、グループのメンバーと協働して商品企画を中心にターゲットの具体化、販売チャネル、プロモーションなどについて考えていきます。 1回の講義の中では、まずはマーケティング論など座学部分を講義形式で学び、その活用例として実務でどのように採り入れているか教えていただきます。その後、グループワーク形式で、その日に学んだことを活かしながら少しずつ商品企画を進めます。 この講義構成について、学生はこう話します。「只野さんがこの講義のために時間を割いて丁寧に準備をしてくださっていることが至る所で感じられます。ここまで私達のためにわかりやすく、そして力がつくように準備してくださっていることに感謝するとともに、絶対に良い商品を作りたいと思っています。」 現場のプロから見たシンジョ生。感性と吸収力に期待! これまで学生に、現場で使う本格的な知識や技術をわかりやすくご教授いただいている、フジッコ株式会社の只野さんに神戸女子大学の学生の印象をお聞きしました。 「ワークシートの記入など、目の前のやらなければいけないことに対し、常に一生懸命ですね。そのため講義内容の飲み込みが早く、教えたことをすぐに自分のものにしていると思います。また、グループワークで活発に話し合う姿が印象的でした。友達同士では明るく話せる子も、グループワークになると黙ってしまうことがよくありますが、それがありませんね。」と只野さん。 講義中の様子 グループワークの活発さは、普段の講義からグループワークを積極的に行っている神戸女子大学の特徴そのもの。それに加え、女子大だからこそ、女性同士でのびのびと積極的に取り組めているのかもしれません! 他にも只野さんは「神戸女子大学の学生のみなさんは感性が素晴らしいと思います。はじめは商品の価値(商品を通じてもたらされる嬉しい期待)を考えることに苦戦していた様子でしたが、具体的な生活シーンを想像しながら「元気にしてくれる豆アイス」「癒される豆アイス」「ほっと落ち着ける豆アイス」「楽しいが増える豆アイス」など、さまざまな意見を出してくれます。どうしても大人は理屈っぽい考えが多くなりがちですが、今日の発表にも『Z世代の彼女たちらしさ』が存分に発揮されています。」と仰ってくださいました。 うちの企画部でも通用するかも!とお褒めいただきました これまでの集大成!想いをぶつける中間発表。 今回の発表内容は、販売ターゲットを絞り込んで具体化する「セグメンテーションとペルソナ設定」、提案する豆アイスを食べるのにぴったりな場面、生活の中での豆アイスの位置づけ、試作品から製品にするための改良点などをまとめた「商品企画コンセプト」、豆アイスがもたらす嬉しい期待とそれを実現する品質との関係をまとめた「ブランドエクイティピラミッド」など。4つのグループがそれぞれ特色ある考えを発表し、それに対して質疑応答を行いました。 ●Aグループターゲット:部活や仕事に日々全力で取り組むZ世代アイスの役割:疲れた時のご褒美、癒して元気にしてくれる提案アイス:『きんとき豆うさぎ』(想定価格250円) きんとき豆が持つ甘味を活かした『きんとき豆うさぎ』。今後、元気を象徴する豆うさぎをデザインに施すそう。 「ライバル商品に勝つための強みは?」という質問に対し「豆が持つ食物繊維をはじめとした栄養素が取れること」と回答するAグループ ●Bグループターゲット:一人暮らしで孤独を感じている女子大生役割:一日の終わりに癒しを与える試作アイス:甘えたくても甘えられない夜に癒しを与えるアイス(想定価格:300円) アイスのイメージはツンデレ彼氏。滑らかな舌触りでやさしい甘さのきんときアイスとナッツの食感でツンデレを表現。 自分たちの体験をもとに、説得力のある発表を行うBグループ 試作品はみんなで試食! ●Cグループターゲット:映える場所や物を求める、SNSを中心に生活する女子大生アイスの役割:SNSに振り回され疲れたところを癒す試作アイス:自分自身と向き合う時間を作るアイス(想定価格:300円) きんとき豆と抹茶を組み合わせ、和の香りで心が落ち着くように。豆が苦手な人でも食べられる豆アイスに。 どういった状況でこの商品が選ばれるのか、図を用いてわかりやすく説明 アイスを「遠方に住んでいる優しいおばあちゃん」と表現し発表するCグループの皆さん ●Dグループターゲット:大人数で初対面の人とでも仲良くしたいZ世代アイスの役割:会話を生み、盛り上げる遊びのツールとして提案アイス:食べて楽しいが増えるアイス(想定価格700円※ファミリーパック1箱) ミルクきんとき味のアイスのまわりをチョコでコーティング。個包装のパッケージにクイズやゲームなど、大人数で楽しめる要素をつける予定。 類似商品を使用し視覚的にイメージを伝えるDグループ 「本気でヒット商品を作りたい」という想いを伝えるべく奮闘した学生たち。それに応えるようにフジッコ株式会社の皆様も真剣に質問を投げかけます。 「滑らかな食感を出すために豆の食感を感じさせないようにしたい」と発表をしたグループに対し、「豆アイスである必要があるのか?」という鋭い質問も。 それに対して、自分達の感性を活かしてその場で「粒あんが苦手でも、こしあんだったら食べることができる人も身の回りにいます。実は私も豆の皮の食感が少し苦手です。だから、豆の風味や味わいを残しながら食感を滑らかにすることで、よりたくさんのZ世代に寄り添える商品になるとイメージしています。」と答えた学生には、社員の方も納得の表情。 その道のプロの考えや空気感にも触れられたこの中間発表は、学生たちを大きく成長させたに違いありません! 山場をひとつ乗り切った学生たちにこの産学連携の魅力を聞いてみた 今回Cグループとして発表していた、心理学部心理学科2年のEさんとIさんにこの講義の魅力を聞きました。 ――この講義の魅力を教えてください。 左:Eさん 右:Iさん Eさん「学生のうちから商品企画に携われることはなかなかありません。自分たちが真剣に考えたものが、店頭で売り出されることになれば、かけがえのない経験になると思います。また、特別講師の只野さんが『学生だから』という甘い対応ではなく、一緒に商品企画をするメンバーの一人として接してくださっているのが非常に嬉しいです!」 Iさん「この講義では、主体的に動くかどうかで、得られる経験が大きく変わってくると感じています。そのような状況を理解しながら学んでいるので、課題に対してより細かく、具体的に考える習慣がつき、自分達の力になってきていると思います。」 前向きに取り組み、回数を重ねるごとに力をつけていく学生は、今回の試作アイスをどのようにブラッシュアップしていくのでしょうか。12月20日には企画する商品の最終プレゼンテーションも控えているそう。みなさんの身の回りのお店で、学生が企画した豆アイスが見られる日はそう遠くないかもしれません!

神女サポート
1,210
2024.9.24
2022年5月に設立された神女ポーアイボランティアセンター(以下、ボラセン)は、学生が主体となって運営するボランティア団体です。設立初年度から神戸女子大学独自の助成金制度「神女support」を活用し、幅広い活動を実施しています。 神女support(学生課外活動助成金制度)とは…学生による自主的な課外活動(地域貢献やボランティア等、地域の課題解決や活性化を推進する取り組み)を支援する独自の助成金制度。活動に必要な資金の助成を受けることができます。詳しくはコチラ! ボラセン設立についてのインタビュー記事はこちら 親子で楽しく、オリジナルの風鈴作り 2024年の夏のとある日、ボラセンが企画したのは風鈴作りのワークショップ。夏ならではのアイテムであり、多くの小学校で夏休みの宿題として出される工作にもぴったりのテーマ。地域に住む親子を対象に参加者を募集し、この日を迎えました。 和気あいあいとしたムードが印象的なボラセンメンバー グループに分かれて準備を進めます。 こちらは何やらボンドと水を混ぜ合わせています… 時間になると、続々と参加者が到着。最初に挨拶と今回の流れを説明したら、早速風鈴作りスタートです! 7組の幅広い年齢の子どもたちが集まってくれました。 今回作るのは紙製の風鈴。まずは風鈴ぐらいの大きさに膨らませた風船にボンドを塗り、白い和紙をちぎって貼り付けます。 カラフルな風船と鈴を用意しました。 ハケを使って風船にボンドを塗っていきます… 難しい部分はボラセンメンバーがサポート。丁寧にボンドを塗っていきます。 手に持っている白い和紙を貼りつけていきます! 白い和紙を貼り終えたら、その上からもう一度ボンドを!そして今度は色つきの和紙を貼り付けます。 好きな色の和紙を選んでちぎりペタペタと貼っていきます。 色とりどりの仕上がりに子どもたちの個性が光ります! 和紙を貼り終わった後はしっかり乾燥させます。乾燥するまでには時間もかかるので、その間はみんなで身体を動かして遊びます!ボラセンの工夫を凝らしたゲームに熱中する子どもたち。たくさんの笑顔が弾けます。 子どもたちの俊敏性が余すところなく発揮された「だるまさんが転んだ」 最後の決勝戦まで白熱したじゃんけん列車。 ペットボトルボーリング。豪快なストライク連発で大盛り上がりでした! 楽しい遊びに熱中しているとあっという間に仕上げの時間に。しっかり乾燥したものは、風船をパン!と割って、短冊に付いた紐を通したら完成! 乾ききらなかったものは自宅に持ち帰って仕上げられるよう、ボラセンメンバーが丁寧にレクチャーしました。 簡単なステップで素敵な手作り風鈴が完成!かわいい! 3年目を迎えたボラセンの活動を振り返る ワークショップ終了後、ボラセン代表の3回生・Hさん、副代表の3回生・Tさん、企画担当の2回生・Mさんを直撃。この1年間の活動について振り返ってもらいました。 写真左から、副代表のTさん、代表のHさん、企画担当のMさん 2024年1月には、令和6年能登半島地震の発生を受け、ポートアイランドキャンパス内にて義援金募金活動を実施。初めての募金活動ながら、たくさんの協力を得ることができました。 5月には毎年恒例の「みなとじまクリーンプロジェクト」を開催。キャンパス周辺を中心に、ポートアイランド内の清掃活動を行いました。新入生にとっては、友達づくりの場にもなったようです。 前年の倍近い70名以上が参加。ボラセンの知名度UPを実感! そして8月初旬には、前年に引き続きポートアイランド市民広場にて行われた「ポートアイランド夏祭り」に出店。前年のわたがし、チェキ撮影に加え、チュロスとキャンドルすくいも提供し大盛況でした。 昨年のイベント記事はこちら 先輩から後輩へとバトンをつなぐ、ボラセンのこれから 設立から2年以上、多くの実績を積んできたボラセン。当初7名だったメンバーも、現在は32名に増えました。 「メンバーが増えたこともそうですし、色々な活動を通して社会福祉協議会や港島自治連合協議会、他大学の団体の方々ともつながりができて、どんどん人の輪が広がっています」とボラセン創設期から所属するTさんは感慨深そうに振り返ってくれました。 1回生の時からボラセンに参加し、2024年度からは副代表を務める3回生・Tさん。 同じく創設期からのメンバーであり、今年度から代表を務めるHさんは、「後輩たちの成長を実感する場面が多いんです。2回生は団結力がありますし、1回生も積極的。すごく頼もしいです」と後輩たちへの信頼を語ります。 2024年度から代表を務める3回生・Hさん。 そんなふたりの後輩にあたる2回生のMさんは、「昨年まで先輩方がやってきたことを、今年は私たち2回生を中心に実践していますが、やはり大変なことも多くて。これまで知らなかった先輩方の苦労に気付かされる日々です」と話します。 2024年度からボラセン内の企画部部長を務める2回生・Mさん。 また、3人はそれぞれ、ボラセンの活動によって自分自身の成長を感じる部分も多いのだとか。 Hさんは「特に代表になってから、人をまとめる力が養われたと感じます。30名以上のメンバーを率いることは想像以上に難しく、毎日が試行錯誤の連続。活動中は全体に気を配りなるべく全員に声をかけたり、会議での話し方を工夫したり、色々と試しながら現在進行形で学んでいます」と話します。 Tさんは「ボラセンに参加していなければ関わることのなかったような多くの人と出会い、アドバイスをいただき、学びの多い日々を送っています。特に、地域の方々とのつながりができてからは、より一層視野が広がったように感じます。また、先輩からだけではなく、後輩から学ぶことも多いですね」と笑顔。 自分たちが主体となって活動を行うからこそ得られる経験を語ってくれました。 Mさんは「私も学内外で同世代だけではなく、子どもから高齢者までさまざまな年代の方と関われることが魅力だと感じていて。皆さんと色々なお話をする中で、自分や周りの友人とは違った考えを聞けたり、新たな視点を得られることがとても魅力的です!」と言います。 今後、新たな試みも計画していると話してくれたボラセンメンバー。「学内でもまだ須磨キャンパスでの認知度は低いので、もっと高めていきたい!」「いずれはポートアイランドの外にまで活動の場を広げたい!」など、目標も尽きません。さらなる躍進が期待されるボラセンにぜひご注目ください! ボラセンのInstagram、ホームページはこちらから ■Instagram ■HP

特集
3,290
2023.10.5
風に舞うバトン、その美しさとリズム感がまるで芸術のようなバトントワリング競技。健康スポーツ栄養学科1回生のKさんは、神戸女子大学で学びながら、バトントワリングで世界のトップを目指す学生アスリートです。新型コロナウイルスによる様々な制限を乗り越えてトップアスリートに成長した彼女の、神戸女子大学での新たな挑戦に迫ります。 情熱の起源!バトントワリングとの運命的な出会い Kさんが小学生の頃、お姉さんのお友達の体操教室に体験に行ったことがバトントワリングとの出会いでした。 バトンをクルクルと回し、天井に届くかと思うほど高く宙に放り投げる演技を見たKさんは、その迫力と美しさを兼ね備えた競技に一目惚れ。持ち前の好奇心で「同じようにできるかな」とさっそく挑戦してみましたが、思わぬ壁にぶつかることになりました。思った通りの動きがなかなかできない難しさに加え、もっとも大変だったのは鉄でできているバトン。思った以上に重く、うまくキャッチできなかった時の痛みは想像以上!しかし、技が成功したときの体験はかけがえのないものでした。 足の下や背後でバトンをキャッチしたり、少しずつ難しい技ができるようになってくるとすっかりバトントワリングの虜に。練習を重ね、大会に出場することになった時には、もちろんジュニア世代でも大会用のメイクをして、競技用の衣装を身に付けて臨みます。初めての大会で技を成功させたときの達成感は、今も記憶に残る貴重な経験だそうです。 練習場は公園!コロナを乗り越えたバトントワリングの軌跡 めきめきと上達するKさんはあっという間に国内のトップ選手へと登り詰めます。しかし、2019年、Kさんが高校1年生のときに世界中が新型コロナウイルスの脅威に襲われてしまいました。他の競技やイベントと同じように、バトントワリング競技も大会の延期や中止に追い込まれます。世界大会に出場する日本代表を決める国内選考会も例外なく延期に。1年後にようやく国内選考会が開催され、結果を残し日本代表に内定したものの、目指していた世界選手権はなんとさらに2年延期という結果に。 その間、競技環境が制限され、なかなか十分な練習に取り組めないという先行きが見えない日々が続きました。そんな中、Kさんが練習場所として選んだのはなんと公園!「他のことをしていても、なんとなくバトンを回したいなという気持ちが湧いてきて。バトンを触っていたいという気持ちが我慢できませんでした。コロナ禍を乗り越えられたのは中学・高校の時のバトン部の同期や先輩・後輩の存在があったからこそ。あの時期は確かに大変だったけどチームのみんなに会えなくても、連絡を取り合い、支え合って努力していた日々はすごく充実感がありました。」と思い出を笑顔で語ってくれました。 コロナ禍も落ち着き始めた高校生3年生のときに、2年間延期されていた「第35回世界バトントワリング選手権大会」がイタリアのトリノで開催。見事日本代表選手として出場し、女子ジュニア部門で世界第2位に輝きました!長い我慢を乗り越え、輝かしい成績で高校生活とジュニア世代を終えた彼女が、次の挑戦として選んだのが神戸女子大学でした。 健康スポーツ栄養学科への道はアスリートとしての直感と食べることへの愛 お姉さんが楽しそうに大学に通っていたこともあり、まずは「大学のオープンキャンパス」に行ってみたい、と感じた高校生時代のKさん。どの大学に行ってみようかと色々なことを調べているうちに、アスリートとして健康スポーツ栄養学科の学びに直感的な興味が湧いたそう。 「食べることが好きなので食に関連した学びができる学科を探していました。オープンキャンパスに行くと、そこで学生スタッフの先輩方が体組成の測定をしてくださったり、さまざまな先生や先輩の研究に触れることができて、楽しい雰囲気も感じましたし、ここで学んでみたいことがたくさんあると思いました。」 「実際に入学して勉強していると、体づくりに栄養がすごく重要だとわかりました。授業では化学式や数字がたくさん出てきて、思った以上に理系の勉強が多いことには少し驚きましたが、丁寧に教えてくださるので、友人と一緒に復習したりして、楽しみながら学べています。クラス単位での行動が多いので、友人が作りやすいことが特徴。新しい仲間と一緒に勉強することって楽しいなと思います。」と笑顔で話してくれたKさんは、健康づくりや競技力を上げるためにどのような食事が大切か日々新しい知識が刺激になっているそうです。 笑顔の裏に秘めた夢!楽しさと学びが交錯する健康スポーツ栄養学科 健康スポーツ栄養学科は、スポーツ経験者の仲間たちが多く、笑顔を絶やさず、いつも楽しい雰囲気に包まれていると教えてくれました。日本代表に輝く実力を持つアスリートであるKさんも、入学前は競技力を向上させるための栄養に関する知識には自信がそれほどなかったと振り返ります。 「入学前は『体づくりには絶対タンパク質!』って思っていたのですが、炭水化物を摂ることで得られるメリットなど授業でどんどん新しいことを学んでいるうちに視点が変わってきたことを感じますね。日々の食事が身体に与える影響や、競技パフォーマンスへの影響を考えるようになりました。」 そんなKさんが自身2度目の世界大会に出場したのは8月、イングランドリヴァプールで開催された世界大会。初めてシニア女子として出場し、2種目で世界第3位に輝きました!まさに日本を代表するバトントワラーのKさんの将来の目標は「様々なアスリートを支援する」こと。競技者としての経験を持ちながら、アスリートを支えるような職業に就くことを思い描き、健康スポーツ栄養学科で学んでいます。 堂々の世界3位に輝きました(写真右) 輝く『JAPAN』のジャージを着用するKさん(写真右) 世界大会後は観光もバッチリ 最後に、将来の目標ではなく「近い目標」について尋ねると、「世界一!」という答えが!夢に向かって努力を続けるKさんは、今回の取材中で最も輝く笑顔を見せてくれました。

キャンパス
1,733
2023.4.4
神戸女子大学では、学生が現場の第一線で働く社会人から、生きた知識や技術を学ぶことができる「産学連携プロジェクト」を実施しています。 2023年3月には本学の地域活性化学生団体「K→osmoseize(コスモシーズ)」が、企業と合同で神戸市須磨区にある商業施設、「須磨パティオ」のPRを行う産学連携プロジェクトに参加。今回はその活動の様子をお伝えします。 課題解決のカギはInstagram!?この日までの活動内容を聞いてみた 今回のプロジェクトの目的は、市営地下鉄名谷駅すぐの商業施設「須磨パティオ」のPR。その方法は須磨パティオとインスタグラマー「神戸人」さん、シンジョ生によるInstagramでの魅力発信です。 このプロジェクトに神戸女子大学を代表して参加するのは、これまでSNSを活用して神戸の魅力発信や、「北野はいからウォーキング」をはじめとしたさまざまなイベントを実施してきた学生団体「K→osmoseize(コスモシーズ)」。 このプロジェクトにおけるこれまでの活動をK→osmoseizeメンバー、家政学科3回生のBさんに聞いてみました!「私たちがこのお話をいただいたのは1月末でした。取り上げる店舗やスポットの選定、訴求コンセプトなどを決める打ち合わせから参加させていただけるということで、喜んで参加を決意しました。3月下旬の投稿を目指し、2月に投稿内容を決める打ち合わせが設けられました。その前にパティオについてもっと知っておこうと、事前に須磨パティオを職員さんに案内していただき、その時受けた説明などをもとに、2月の打ち合わせでは6つのコンセプトを提案。最終的には、昨年リニューアルされた芝生の広場を使って、『おしゃピク』をテーマにした投稿を行うことに決まりました。」 おしゃピクとは…可愛いカトラリーや敷物などのアイテム、写真映えのする食事などを用意して、おしゃれな空間で写真撮影も行いながらピクニックを楽しむことです。SNSにハッシュタグ「#おしゃピク」をつけて投稿することが最近のトレンド! 投稿の出来を左右する撮影準備。学生の発想×プロの経験 取材日は、インスタグラマー「神戸人」さんと投稿用写真の撮影日。まずはシンジョ生と神戸人さんがそれぞれ事前に用意した小道具のお披露目です。 神戸人 (@kobejin1218)さんって?2万人以上のフォロワーを擁する神戸を愛するインスタグラマー。数々の投稿には神戸市民はもちろん、かつて神戸に住んでいたことがある方も、きっと「いいね!」を押したくなる神戸の魅力がたくさん! ここで神戸人さんが驚いたのが、シンジョ生が持参した“ハムスターが遊ぶための小さな木製ボール”。この木製ボールにランチョンマットを敷いて、食材などを入れようというアイデアです。 写真左から、K→osmoseize(コスモシーズ)副代表のTさん、Bさん、インスタグラマー神戸人さん 神戸人さんから、「飾りつけといえば“花”というような固定概念ではなく、形がかわいいからという直感的な理由で新しいものを取り入れる発想が面白いです。シンジョ生にアドバイスをすると、そこに自分たちの発想を加え、想像以上の結果を見せてくれるので、一緒に活動していると、こちらも良い刺激がもらえます。」とお褒めいただきました。 自分たちで下見をし、撮影構図を考えて用意してきた小道具を披露しました。 その後は、この日の撮影で使う食材の買い出しに。 なにがSNSで映えるのかを考え、パティオを散策。コーヒーやパン、おにぎり、お花など「ピクニック」感を演出するさまざまな商品を須磨パティオのテナントで購入しました。改めて館内をぐるりと回ると、こんなにも魅力あるお店があるのかと驚きを隠せませんでした。 かわいいフォルムのおにぎり発見! 写真に彩りを持たすためのドリンクを購入する際は、神戸人さんからアドバイスをいただくシーンもありました。 グレープなど鮮やかな色のドリンクと炭酸水を混ぜることで、気泡が活きた綺麗な「写真映えドリンク」が作れるそうです 次はいよいよ撮影へ! 天気にも恵まれ、いざ撮影!自分たちのイメージを形に 今回の撮影テーマは「ピクニック」。パティオ内にある昨年リニューアルした芝生の広場で撮影を行いました。 撮影では自然光の当て方や被写体の設置方法による空間や奥行きの活かし方など、神戸人さんから、プロならではのアドバイスをいただくシンジョ生。いただいたアドバイスはその場ですぐに実践! 春らしく桜の色で統一感もあっておしゃれです 配置や食材を入れる容器など、試行錯誤を繰り返しながら完成した「おしゃピク」を表現した一枚がこちら。 この日の撮影素材を使用した投稿や、須磨パティオのどのお店で購入できるのかは、手のひらパティオ 〈須磨パティオ Official〉、神戸人さんの記事をご覧ください。 この投稿をInstagramで見る 神戸人(@kobejin2018)がシェアした投稿 この投稿をInstagramで見る 手のひらパティオ 〈須磨パティオ Official〉(@tenohira.patio)がシェアした投稿 この投稿をInstagramで見る 手のひらパティオ 〈須磨パティオ Official〉(@tenohira.patio)がシェアした投稿 この投稿をInstagramで見る 手のひらパティオ 〈須磨パティオ Official〉(@tenohira.patio)がシェアした投稿 撮影後に今回の産学連携プロジェクトの感想をBさんに聞いてみました。「私たちはSNSを活用し、神戸の魅力を数多く発信してきました。しかし、これまではほとんどが独学での投稿だったので、今回いただいた専門的なアドバイスはとても刺激的でした。また、産学連携プロジェクトでは本物のビジネスに携わることができるので、周りよりも一足先に成長できている実感があります。もちろんビジネスマナーなども自然と身につくので、今後の就職活動でも活かしていきたいです。」 このプロジェクトを取りまとめる広告代理店の方も「これまであらゆる活動を積極的にされていたという背景が見えるほど、言葉遣いや対応がしっかりされている印象です。産学連携を活かしたこのプロモーションがパティオの活性化に繋がることを期待しています。」とシンジョ生を評価してくださっていました。 今回のプロジェクトが結果を残し、次の新たなる活動へと繋がることを願っています!またこのように、学生が成長できる学びの場を提供し続けられるよう、神戸女子大学はこれからも地域との結びつきを大切に、「産学連携プロジェクト」を積極的に企画していきます!!